鳥取木鶏研究会 例会 平成21年1月5日
第六講(昭和53年5月16日)
運命と義命
何時の間にか予定の半ばにある五回まで講義を進めてまいりましたので、易の原義というものについては、かなり理解されたことと思います。何事も総てそうでありますが、根本が確立しませんと、先へゆく程わからなくなるもので、特にこの易学というものは、根本義が明確になりませんと、進めば進む程わからなくなり、とんだ誤解に陥ったり、どうかすると曲学とか、或いは偽学などというものになりがちであります。
これによりますと易というものは、「算木筮竹」で占ってそれにより諸般の人間の思考、行動というものを決めるものというような、極めてたわいない常識、俗識でかたづけてしまうというようなことになるのであります。
易学は造化の学問
皆さんは、既によく理解されたと存じますが、易学は「天地人生を通ずる創造進化、あるいは変化の原理」を説いた造化の学問であります。
我々の存在、生活、行動というものは、いかなる原理原則を含むものであるか。つまり「義」と「理」でありますから、「義理の学」、あるいは「理義の学」と申します。
易学は造化の学問
つまり天地人生を通ずる創造進化、これを体認実践する学問である。
―従って易には、天の真理から我々のいかに生きるべきか、という実践、行動に至るまで六つの意義があるというお話を致しました。
易学は原因結果の理法
天地・人生というものは運命である。運はめぐる、動くという文字で、常に活動し変化してやまぬものであり、命とは信ずると信ぜざるとに拘らず、必然にして絶対なるものである。
そこで運命というものには、その中に複雑な意味が含まれておる。即ち、「原因結果の理法」が含まれておる。それにもとづいて我々は思索し行動しなければなりません。
易学は命理、数理の学
その運命の中の複雑な因果の関係理法というものを「数」といいます。つまり、運命は「命数」であり、その中に「理」を含んでおるから「命理」や「数理」と言います。
一般に数理というと数学に関する原理原則のように思いがちですが、易学では、天地自然、自然と人間を通ずる複雑な理法と、これをいかに実践するかという意味を含んでおるのであります。
易は変化と実践の学問
そこで易の六つの意味の中で、特に大事なのは、「おさめる(修、治)」という意味でありまして、易を「おさめる」と読みます。
易世という文句は、世をかえるという意味よりも、世をおさめるという意味であります。
易世革命とは、世を治め命を革めるということであります。
(易姓革命とはまた別で、この方は革命王朝の姓の変革です)、易学というものは、どうにもならない、所謂宿命を尋ねる学問ではなく、我々の人間そのもの、人生そのものがいかに成立っており、いかになすべきものであるか、という変化と同時に実践の学問であります。
.天地自然の学問
以上を五回に亘って説明したわけでありますが、この根本原理が十分頭に入っておりませんと、やればやる程わからなくなり、或いは邪経邪路に入りやすい。
我々の学問はどこまでも正学でなければなりません。正学とは、天地人間を通ずる正しい原理原則が外れないで、これに従う学問であります。つまり概念や論理の遊戯ではなく、厳粛な自然と人生を通ずる理法、真理とその法則、これに従って我々が正しく行動するための学問であります。
義命の学問
そこで運命とは、我らいかにあり、いかになすべきかという義命の学であるということが出来る。
これは人間個人の存在から、国家民族の存在まで皆通ずることであります。我々は、運命でなく、常に義命というものを立てていかなければなりません。それを説き、それを明かしてくれる一番基本的な学問がこの易学であります。
.太極より六十四卦
この宇宙人生を通ずる創造、即ちクリエーションと変化、造化の根源を「太極」と言って、これを近代学で申しますと、「創造概念」であります。「太」という字は、存在と同時に行動を表す文字であります。
そこで易では、太極を符号の(![]() )で表現する。これは単なる線ではなく、創造概念を表すもので、全であり、一であり、絶対であります。その太極と同じ符号で「陽」(
)で表現する。これは単なる線ではなく、創造概念を表すもので、全であり、一であり、絶対であります。その太極と同じ符号で「陽」(![]() )を現し、これに対して真ん中を切った符号(
)を現し、これに対して真ん中を切った符号(![]() )を「陰」とします。
)を「陰」とします。
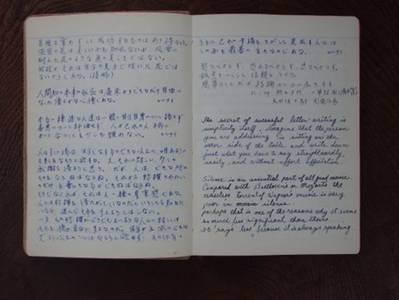
平成21年1月5日 徳永圀典記