| 1日 |
十翼 |
十翼とは、繋辞伝上下、彖伝上下、象伝上下の六篇に、文言・序卦・説卦・雑卦 |
の四伝、合わせて十篇を言う。伝とは衍義・解説の意味である。易経の彖辞・象辞を文主・周公の作とする以上、十翼を孔子の作とすることは当然の妙案であるが、その非科学的なことはやがて明らかにされた。 |
| 2日 |
生の形而上学、中の実践哲学 |
この中彖・象の二伝は最も古いものを存しており有韻の文を含んでいる。次に重要なものに繋辞伝と文言伝で繋辞伝は易学概論であり文言伝の序論ともいうべきものであるが錯簡脱落が多い。
|
文言伝は今日乾坤二卦にだけ存しているが、古くは全卦についてあったものと思われる。繋辞伝の各論ともいうべきものである。これらによって剛と柔とを原理とした古易に、陰陽相対性理論が確立され、生の形而上学、中の実践哲学が樹立された。
|
| 3日 |
大象 |
戦国から秦代にかけて、子思学派の手になったものであろうが、卦に関して別に解説を立てたものが説卦伝で総論的なものであるが、この各論にあたるものが大象である。
|
現行易経の「象に曰く」とあるのがそれである。往々四書の大学と共通の文がある。序卦・雑卦は占筮家の易説で稍々後期の作である。 |
| 4日 |
易は本来は「象数」 |
易経の体制が成立するにつれて、易の研究も、学問実践(義理)を旨とするものと、占筮、霊覚(象数)を旨とするものとの二派の別が明らかになった。漢代は象数派が盛んで、宋・明に最も義理の易が発達したのであるが、私はもとより義理の学を重んずる者である。 |
聖人は卜筮を煩はさず(左伝桓公十一年)。
善く易を為むる者は占はず(荀子・大略)が人間の進歩であり、権威であることを知っているが、然し易は本来象数であり、占へるだけの純一無雑の徳や霊覚の力を持つ人間の無くなることを深く惜しむものである。三国・呉の愚翻の象数を旨とする学問など永久に珍重されるべきものである。 |
| 5日 |
易の六義 |
易に三義(易簡・変易・不易)があるということは鄭玄以来の通説であるが、理解を深める為に、私は進んで六義を挙げたいと思う。
|
(一)は勿論、易簡ということである。乾は易を以て知り(つかさとどり)、坤は簡を以て能くす(繋辞上)という易簡である。自然は単純を愛するとコペルニクスも言っている。自然を熟視していたニュートンも、自然は常に単純であり、何らの自家撞着をもたないのであると語っている。 |
| 6日 |
易わる、易わらぬ |
(二)、変易、かわるという意味。これは改めて説くまでもあるまい。
(三)、不易、易るということは易はらぬということを予想する。易らぬも |
のなくして、易ることは無い。赤が黒に易るということは、その奥に不易の「色」なるものがあるからである。これも詳説することを省く。 |
| 7日 |
易と夷 |
(四)は易るという字は夷と同音相通じ、感覚を超越した神秘的なものの意である。孔頴達以来、易にイという音(去声)とエキという音(入声)とをわけるが昔は皆エキという音が相通じたらしい。 |
(五)、易が、延・信、即ちのびるという意に用いられたことである。「悪の易ぶるや、火の原を焼くが如く」と左伝・隠公六年に出ている。造化の発展に合致する。 |
| 8日 |
治とか修の意 |
(六)、治とか修とか整の意である。詩経に「禾易ひ畝に長ず」、孟子に「其の田疇を易む」、論語に「喪は其の易はんよりは寧ろ戚め」とあるが、 |
天地の道を観て、人間の道を治めるのが易であるから、この用例も意味深い。
乾の文言伝初九に、不易乎世。不成乎名とある易も世を易めずと解すれば次の句とよく照応すると思う。 |
| 9日 |
易という文字の由来 |
(一)は、日と月とを合わせたものとする。然し下体は月ではないと、段体裁が説文で否定している。 |
(二)は蜥易・えんてい・守宮の象形とする。許慎の説文によると、壁にはりついているのが、えんてい(やもり)、草庭にをるのが蜥易(とかげ)。守宮は「いもり」であろう。
|
| 10日 |
易という文字の由来 2 |
秦始皇帝の時、これを献上したものがある。宮中の鑰を守らせたところが、誰も寄りつかなかったので、守宮と言うと。蜥易は一日に十二回色を変えるので易というと。大英百科全書によれば、それはカメレオンのことであろうと云っている。
|
(三)、葛城学蒼氏はその易字攷に、月と勿との合字としている。これらは光の象、春秋中期に土圭(日時計)を用いるまで、月光を用いて時を測った。古代人が時という観念を得たのは、日からでも星からでもない、月からであることは、とき・つき・としと日本でも同根であると説いている。易はゆうであると。 |
|
太極より六十四卦へ |
|
|
| 11日 |
太極と両儀 |
易を学ぶ者は先ず自ら、太極より両儀・四象・八卦・六十四卦・三百八十四爻を展開させてみるのが一番速く確かに会得することができる。 |
太極は絶対者であるが、相対(待)の形式で自己を表現する。即ち陰・陽である。これを両儀という。儀とは配偶の意である。
|
| 12日 |
太極と陽・陰 |
太極を─で表し、これと同じ符号で陽─を表し、--を陰とする。 |
陽が造化の活動・表現・発展を代表するから、陽は太極と同じ形式を用いるのである。 |
| 13日 |
四象 |
陽にも、陽の陽なるもの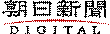 と、陽の陰なるもの と、陽の陰なるもの とあり、 とあり、 |
陰にも、陰の陽なるもの と、陰の陰なるもの と、陰の陰なるもの とがある。これが四象である。 とがある。これが四象である。 |
| 14日 |
老と少の陽と陰 |
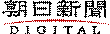 を老陽・夏、 を老陽・夏、 を少陽・春、 を少陽・春、 |
 を小陰・秋、 を小陰・秋、 を老陰・冬とする。 を老陰・冬とする。 |
| 15日 |
小成の卦 |
これを更に「陽の陽の陽なるもの」 と、 と、 |
「陽の陽の陰なるもの」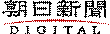 という風に展べてゆけば八卦ができる。これを「小成の卦」という。 という風に展べてゆけば八卦ができる。これを「小成の卦」という。 |
| 16日 |
八卦図
|
父―乾天 >老陽
少女―兌澤 >陽─
中女―離火 >少陽
長男―震雷
>太極
|
>太極
長女―巽風>少陰
中男―坎水>陰
少男―艮山>老陰
母―坤地
|
| 17日 |
八卦は自然と人間を表す |
八卦はこれを自然現象に配当すれば、天・澤・火・雷・水・山・地であり、これをその性情より言えば、健・説・麗・動・入・陥・止・順であり、更にこれを家族の成員に配すれば、父母及び三男三女に当たる。 |
即ち乾坤を以て父母と為し、また繋辞伝に、陽卦多陰、陰卦多陽とあるに則り、一陽二陰の卦を男子、一陰二陽の卦を女子と為し、その長幼を定むるには、卦主たる一陽一陰が初爻に在るを長、二爻に在るを中、三爻にあるを少とする。 |
| 18日 |
実在の循環関係を表す卦 |
長男は父の後を継ぐべき者なるが故に父に属し、長女は家政を助くべき者なるが故に母に属し、少女は最も父に近づき親しみ、少男は最も母に近づき親しむ実際の姿がおのづから表されている。詳細は後に詳説する。 |
このようにして、三爻より成る八卦を六爻組織にまで展開すると六十四卦ができあがる。これを大成の卦という。前漢の焦?は六十四卦を更に二乗して、四〇九六卦まで発展させたが、煩瑣なばかりで成功しなかつた。 |
| 19日 |
卦爻と変化 |
太極より発展して出来た六十四卦を「本卦」あるいは「原卦」とする。 |
陰陽変化の理法に従って、卦全体或は各爻の変によって生ずる様々の卦を総じて「変卦」と名づける。 |
| 20日 |
総卦と錯卦
|
その中、特に重要なのは「総卦」と「錯卦」とである。総卦とは、本卦を逆に見た、上から見た、つまり百八十度転回させた卦である。水雷屯で言うと、山水蒙である。 |
人間の屯(なやみ)は天より見れば、大所高所より見れば蒙昧である。この本卦を裏返したもの、陰陽逆転したものを錯卦という。屯の錯卦は火風鼎である。悩みは即ち、いかにこれを塩梅して革新するかである。 |
| 21日 |
六十四卦悉く錯綜して組織
上経の錯卦(右)
|
|
乾為天
|
|
坤為地
|
|
|
水雷屯
|
|
山水蒙
|
|
|
|
水天需
|
|
天水訟
|
|
|
地水師
|
|
水地比
|
|
|
| 22日 |
|
|
風天小畜
|
 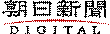
|
天澤履
|
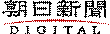 
|
|
地天泰
|
|
天地否
|
|
|
|
天火同人
|
|
火天大有
|
|
|
地山謙
|
|
雷地豫
|
|
|
| 23日 |
上経の錯卦2(右)
|
|
澤雷随
|
|
山風蠱
|
|
|
地澤臨
|
|
風地觀
|
|
|
|
火雷噬こう
|
|
山火賁
|
|
|
山地剥
|
|
地雷復
|
|
|
| 24日 |
|
|
天雷无妄
|
|
山天大蓄
|
|
|
山雷頤
|
|
澤風大過
|
|
|
坎為水
|
|
離為火
|
|
|
以上、乾為天と坤為地とを出発として、
坎為水と離為火とに終る三十卦を以て上経とする。
|
| 25日 |
下経の三十四卦 |
|
澤山咸
|
|
雷風恆
|
|
|
天山遯
|
|
雷天大壮
|
|
|
|
火地晋
|
|
地火明夷
|
|
|
風火家人
|
|
火澤けい
|
|
|
| 26日 |
|
|
水山蹇
|
|
雷水解
|
|
山澤損
|
|
風雷益
|
|
|
澤天夬
|
|
天風?
|
|
澤地萃
|
|
地風升
|
|
| 27日 |
|
|
澤水困
|
|
水風井
|
|
澤火革
|
|
火風鼎
|
|
|
震為雷
|
|
艮為山
|
|
風山漸
|
|
雷澤帰妹
|
|
| 28日 |
|
|
雷火豊
|
|
火山旅
|
|
巽為風
|
|
兌為澤
|
|
風水渙
|
|
水澤節
|
|
|
風澤中孚
|
|
雷山小過
|
|
|
水火既濟
|
|
火水未濟
|
|
これに対して本卦と錯卦とを関連させてその十二支を以て完体とする聯卦の説があるが省略する。
|
| 29日 |
上爻 五爻 四爻 三爻 二爻 初爻 |
爻は下より初爻、二爻、三爻、四爻、五爻、上爻と順に上へ進む。一番下の爻は一爻と言わずし |
て初爻と言い、一番上の爻は六爻と言わず、上爻と言う。易の卦は下から始まって、上に至るとする。 |
| 30日 |
「卦爻と三才」「爻位」 |
「卦爻と三才」。三爻から成る八卦も、六爻から成る大成の卦にも、天人地の三才にあてはめる場合がある。地は現実、天は理想、火は実現と言うことができる。「爻位」。いずれの卦でも、初爻と三爻五爻は奇数で、陽の位、二爻と四爻と上爻とは偶数で、陰の位である。そして卦を説く場合、若し初爻に陰のある時は陰爻陽位在りと、或は二爻に陽爻ある時には、陽爻を以て陰位に居るなどという。そして陽の位に陽爻ある場合、陰位に陰爻ある場合を正 |
となし、それと反対に陽位に陰があり、陰位に陽爻のあるを不正とするのである。正を吉とし、不正を不祥とする。但しこの例外をなす場合もある。陰を以て陽位に居り、陽を以て陰位に居るは両者の性を折衷するとなすこともある。卦の性質如何に由って定まる。一般には言い難い。六十四卦中六爻悉く正位を得たものは、水火既濟の一卦のみであるが、かく悉く正を得るのは一面安定の状で却って無活動のすがたとも成る。
|
| 31日 |
中爻 |
何れの卦に於いても、最も大切なのは中爻である。中とは上下卦六爻の中で、二爻は下卦の中であり、五爻は上卦の中である。
|
多くの場合、下卦の中爻は、下卦全体の代表位となし、五爻は上卦の中位で、上卦の代表位であり、また全卦の主位である。 |