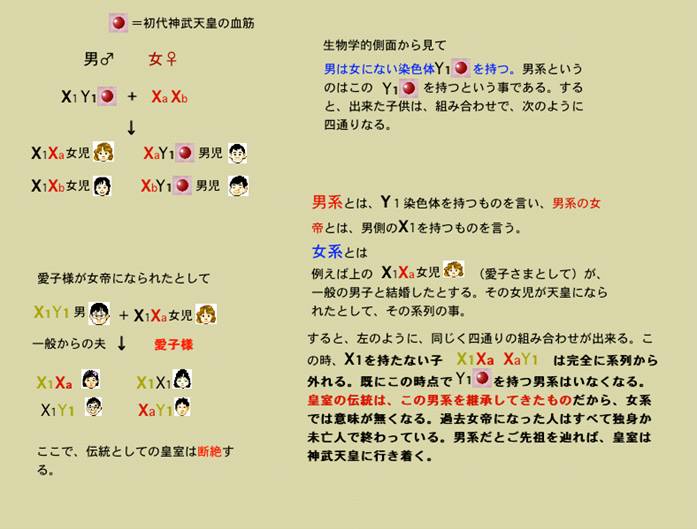| 1日 |
運命と義命 |
何時の間にか予定の半ばにある五回まで講義を進めてまいりましたので易の原義というものについては、かなり理解されたことと思います。何事も総てそうでありますが、根本が確立しませんと、先へゆく程わからなくなるもので、特にこの易学というものは、根本義が明確になりませんと進めば進む程わからなくなり |
とんだ誤解に陥ったり、どうかすると曲学とか或いは偽学などというものになりがちであります。これによりますと易というものは、「算木筮竹」で占ってそれにより諸般の人間の思考、行動というものを決めるものというような、極めてたわいない常識、俗識でかたづけてしまうというようなことになるのであります。 |
| 2日 |
易学は造化の学問 |
皆さんは、既によく理解されたと存じますが、易学は「天地人生を通ずる創造進化、あるいは変化の原理」を説いた造化の学問であります。 |
我々の存在、生活、行動というものは、いかなる原理原則を含むものであるか。つまり「義」と「理」でありますから、「義理の学」、あるいは「理義の学」と申します。 |
| 3日 |
易学は造化の学問 |
つまり天地人生を通ずる創造進化、これを体認実践する学問である。 |
従って易には、天地の真理から我々のいかに生きるべきか、という実践、行動に至るまで六つの意義があるというお話を致しました。 |
| 4日 |
易学は原因結果の理法 |
天地・人生というものは運命である。運はめぐる、動くという文字で、常に活動し変化してやまぬものであり、命とは信ずると信ぜざるとに拘らず必然にして絶対なるも |
のである。
そこで運命というものには、その中に複雑な意味が含まれておる。即ち、「原因結果の理法」が含まれておる。それにもとづいて我々は思索し行動しなければなりません。 |
| 5日 |
易学は命理、数理の学 |
その運命の中の複雑な因果の関係理法というものを「数」といいます。つまり、運命は「命数」であり、その中に「理」を含んでおるから「命理」や「数理」と言い |
ます。
一般に数理というと数学に関する原理原則のように思いがちですが、易学では、天地自然、自然と人間を通ずる複雑な理法と、これをいかに実践するかという意味を含んでおるのであります。 |
| 6日 |
易は変化と実践の学問 |
そこで易の六つの意味の中で、特に大事なのは、「おさめる(修、治)」という意味でありまして、易を「おさめる」と読みます。易世という文句は、世をかえるという意味よりも、世をおさめるという意味であります。
易世革命とは、世を治め命 |
を革めるということであります。(易姓革命とはまた別で、この方は革命王朝の姓の変革です)、易学というものは、どうにもならない、所謂宿命を尋ねる学問ではなく、我々の人間そのもの、人生そのものがいかに成立っており、いかになすべきものであるか、という変化と同時に実践の学問であります。 |
| 7日 |
天地自然の学問 |
以上を五回に亘って説明したわけでありますが、この根本原理が十分頭に入っておりませんと、やればやる程わからなくなり、或いは邪経邪路に入りやすい。我々の学問はどこまでも正学でなければなりません。 |
正学とは、天地人間を通ずる正しい原理原則が外れないで、これに従う学問であります。つまり概念や論理の遊戯ではなく、厳粛な自然と人生を通ずる理法、真理とその法則、これに従って我々が正しく行動するための学問であります。 |
| 8日 |
義命の学問 |
そこで運命とは我らいかにあり、いかになすべきかという義命の学であるということが出来る。これは人間個人の存在から、国家民族の存在まで皆通ずること |
であります。我々は、運命でなく、常に義命というものを立てていかなければなりません。それを説き、それを明かしてくれる一番基本的な学問がこの易学であります。 |
| 9日 |
太極より六十四卦
|
この宇宙人生を通ずる創造、即ちクリエーションと変化、造化の根源を「太極」と言って、これを近代学で申しますと、「創造概念」であります。「太」という字は、存在と同時に行動を表す文字であります。そこで易では、太極を符号の(ー)で表現する。これは単なる線ではなく、創造概念を表すもので、全であり、一であり、絶対であります。その太極と同じ符号で「陽」(ー)を現し、これに対して真ん中を切った符号(- -)を「陰」とします。
|
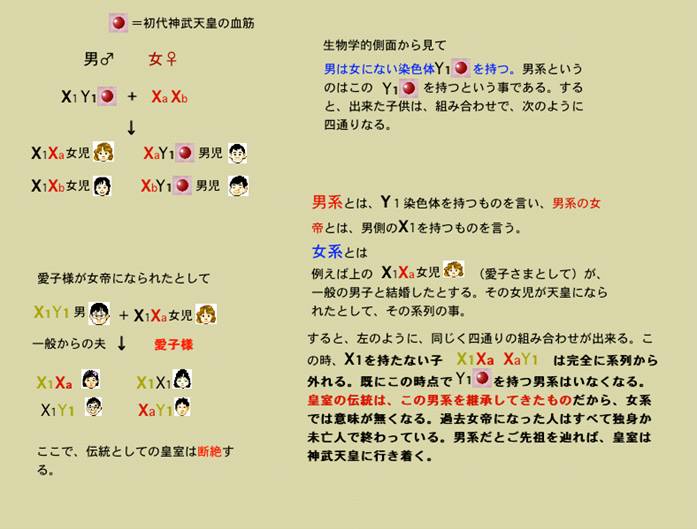
|
| 10日 |
両儀 |
我等いかになすべきかという行動、或いは造化は、いかに存在し、活動するかということは「義」であります。
|
ここでは人間が肝腎でありますから、イーにんべんを付けて「儀」の字を使い、陰陽ですから「両儀」と言って限りなく発展するわけであります。 |
| 11日 |
四象 |
また「陽」は、造化の活動、表現、発展を代表するから太極と同じ形式を用いますが、「陽の陽なるもの(老陽)」と「陽の陰なるもの
|
(少陰)」があります。陰にも、「陰の陽なるもの(老陰)」と、「陰の陰なるもの(少陽)」があって、これが「四象」であります。ー上図を参照
|
| 12日 |
八卦 |
さらに「陽の陽の陽なるもの」と「陽の陽の陰なるもの」という風に展開してゆけば「八卦」が出来ます。 |
八卦は、これを自然現象に配当すると、「天・澤・火・雷・風・水・山・地」となります。 |
| 13日 |
八卦・四象・両儀 |
太極という根元は下記で構成されている。
「両儀」 陽 陰
|
「四象」老陽 少陽 少陰老陰
「八卦」天・澤・火・雷・風・ 水・山・地
|
| 14日 |
「両儀」 |
造化の根元の太極が、陰陽の両つに分かれる。 |
陽(ー)と陰(ー -)である。 |
| 15日 |
「四象」 |
陰にも陽にも夫々究極がある。
老陽  少陽 少陽 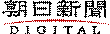 |
少陰  老陰 老陰  |
| 16日 |
両儀を更に発展させると、八卦となる。 |
天澤 火雷
|
風水 山地 |
| 17日 |
六爻に展開 |
この八卦を六爻組織にまで展開すると六十四卦が出来上がる。前漢の焦こうは、六十四卦を二乗して、四千九十六卦まで発展させておりますが、これは価値が無く、結局六十四まで展開すればそれで十分となりました。 |
そこで易経は六十四卦に落ちついたのであります。その卦に一つ一つ名前が出来ております。色々のテクニカル・ターム、専門用語が出来ております。この基本的な用語の正しい意味を知りませんと、行けば行く程分からなくなりますから、面倒ですけれども、最初にこの専門用語をよく理解し、これを活用できるように消化するという努力が必要であります。 |
| 18日 |
卦爻と変化 |
易は天地人生というものが、我々の見るように、一つの形、物象、万物というものになって表現され、活動しておるわけでありますから、どうしても形に表現しなければなりません。 |
原理原則だけでは、抽象的思惟にとどまり一般の人間にはわからない。これを解明し、開発していくためには、どうしても実証しなければなりません。象徴に俟たなければなりません。 |
| 19日 |
爻 |
また、易は天地人の三才でありまして、これが表となり、裏となり、外となって変化していくわけでありますから、我々の生活、存在と活動を一つの象徴にしないと議論、研究を進めていくことができません。
|
これを一つの線で表し天地人三才を象徴し、それを更に展開して六爻という。その一つ一つが爻であります。 |
| 20日 |
爻 |
上から、上爻、五爻、四爻、三爻、二爻、初爻。
|
上の三本を「外卦」、下三本を「内卦」という。
|
| 21日 |
爻 の説明 |
こうして出来た全体を卦あるいは卦という。六爻のうち下半分を「内」と言い、上半分を「外」と言います。
|
つまり易は六爻から成り立っておって、内卦と外卦とにわけて解説され、これが色々と変化するものですから、この根本を「本卦」と言います。「本卦帰り」等という言葉はここから出たものであります。 |
| 22日 |
本卦からの変化
|
本卦から、どういうふうに変化するか、その変化することを変ずる卦、即ち変卦、或いは進行するという意味で「之(ゆく)卦」ともいう。
|
その中に、二・三・四爻、三・四・五爻。この二つを重ねたものを「互卦」と言い、交錯するという意味であります。互卦(ひとつの卦があった時、その2~4爻を下卦とし、3~5爻を上卦として作った卦のことです。)
|
|
参考 |
六十四卦 図解 |
|
| 23日 |
互卦 |
例えば、「天火同人(」の卦は、下が火で上が天でありますが、その中には、二・三・四爻、これは風であります。 |
それから、三・四・五爻に天、これが圧縮されている。つまり「天火同人」の卦は、「天風こう」という互卦をもっておると見るのです。これが非常に大事であります。 |
| 24日 |
綜卦 |
天火同人の卦を逆に上から見るとどうなるか、これを綜卦と言い例えば天火同人を上から見ると
|
これは「火天大有」であります。つまり天火同人の綜卦は、火天大有であります。 |
| 25日 |
錯卦
|
またこの卦を裏返ししたもの陰陽を逆転したものを「錯卦」という。例えば「乾為天(」の錯卦は「坤為地(」であります。このように一つの卦が出ますと、少なくともこれだけは見なければなりません。
|
本卦に基づいて変卦(之卦)を知り、その間に含まっておる互卦を見て変卦を理解し、綜卦あるいは、錯卦を知って推察していくわけですから、いわゆる千変万化であります。 |
| 26日 |
易は変化と行動の学問 |
然し、その変化には原則があって濫りに変化しません。その原則に基づいてこれを自由に推察していくものですから易は変化と行動の学問であります。処が、どうかすると宿命観に陥りがちですが、決してそうでなく、易は創造進化の原理を明らかにして、どこまでも変化向上、或いは進化向上していく学問であります。 |
これを更にしっかりと知っておかなければなりません。これをいい加減にしておりますと、やればやる程、分からなくなります。易学というものは、宿命を尋ねる学問ではなく、創造進化、我という存在をどこまでも創造進化させていく学問、即ち義命の学問であります。 |
| 27日 |
易の卦の配列 |
そこで、易の卦の配列でありますが、これは六十四の範疇に分類して、それを組み立てたのが六十四卦、これで易経が出来ておるのであります。この卦の配列が又、非常によくできております。非常に長い年月の体験と思索に基づく結論でありまして、ただ雑然と卦が並んでいるのではありません。 |
例えば、先程お話をしました、「天火同人」の卦について申しますと「天」と火とが組み合わさって天火同人の卦ができております。皆さんはこの近鉄の同人です。だから、ここに集まっておられるのは、同人の卦と言えばいいわけです。 |
| 28日 |
卦はシンボライズ |
即ち、ここに一つの同人の卦が実在しておる。そういうふうにシンボライズするのが卦という意味です。まさに本日の講座は、近鉄同人の卦になっておるわけです。 |
つまり、この同人の中で、今日の主催者、代表者は五爻にあたります。その事務を執る人、世話役が二爻になるわけです。こういうふうに卦は色々のものを象徴いたします。
|
| 29日 |
大有 |
易経を御覧になりますと、天火同人の次に、「火天大有」をおいてあります。
|
これは大いに保つ、つまりこれだけの人間が集まる(同人)とそこに何らかの意義、作用、勢力、内容等がでるわけであります。これが「大有」であります。 |
| 30日 |
易の配列の妙 |
処が、このように集団となり、綜合勢力が強くなると余程注意しないと、矛盾衝突等問題がおこる。そこで、「火天大有」の次に、「地山謙」の卦をおいてあります。
謙は謙遜の謙でありまして、内 |
省して、お互いにけちな欲等を捨て、譲りあっていかなければ、事業は伸びない。謙譲の精神と、行動の原理をもたなければならぬという戒めでありまして、このように易の配列は、考えれば考える程、頭のさがる思いがするのであります。 |
| 31日 |
安心の前は計画 |
一同内省して謙譲の徳を発揮致しますと、安心して計画を立て、実施をすることができるのであります。そうなると、ゆとりもでき、楽しみも湧いてきます。
そこで易経は、地山謙の次に、これを引っ繰り返した、 |
「雷地豫」の卦をおいております。豫という字は、あらかじめ、先を見るという意味がありまして、先が見えるから色んな計画を立てることができます。そういう意味を含んだ雷地豫の卦を配しております。 |