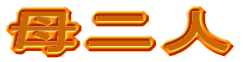
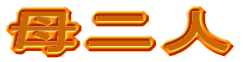
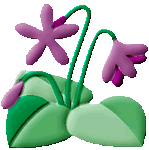 森本 担子
森本 担子
「母」「おかあさん」、この言葉を見たり聞いたり、ひとり心に思うとき、私は胸の中にじわっと水が沸いてくるようないい知れぬ孤独感に襲われる。
私には本当に私をこの世に送り出した母というものがあったのだろうか。
子供の頃は、私には母がなくどこかで拾われてきたのではないだろうかと本気で考えたこともあった。
阪神タイガースの元監督で、今は亡き村山実氏がある雑誌にこんなことを書いておられた。
「母が亡くなった数日間は、僕ら男兄弟五人が外に出る時など、先を争って玄関に行き、母が生前に履いていた下駄を取り合って履いた。ほとんど僕が一番に履いたけど弟に取られた時は悔しくて怒ったりした。それほどまでに兄弟は母を独占したかったし、母の温もりを素足に感じたかった」
この随想を読んだとき私は、男の子がこんなに慕うなんて、母とはそれほど大切な存在なのか、死んでからでも子供たちにそんな思いを残すものなのかと、しんみり「母」というものを考えながら、自分の運命を見つめた。
私の母は私が一歳半の時、結核を病んで亡くなった。昭和九年四月十五日のことである。母二十五歳の春であった。
「久松山の桜がせいいっぱい咲き、幾日もたたずはらはらと散っていくとき、いつもお前のおかあさんを思い出していた」
と、祖母が成人した私によく話してくれた。
私の父母の家は、久松山の麓の閑静な城下町にあり、風花が舞って縁側に届く頃に聞く祖母の話は、私の心にも重く響くようになった。
現在九十五歳の父が書き留めている「思い出の記」がある。
昭和九年四月十五日
愛妻、春枝死す。昨年八月頃から足が痛いと言い、十月中旬発病。肺結核と診断され、それは不治の病となった。昨日の十四日は旧暦の三月二日で、宵節句であり、階下の床の間にひろこの初節句の「ひなさん」を飾った。翌十五日の朝、妻の容態は急変し呼吸困難になり医者を呼び家族が見守った。医者は今日中が難しいという。覚悟を強いられる。母は、こんなことにならないようにと思って雛さんを飾ったのに、と言って泣きながら雛さんを箱に入れた。夜になってから虫の息となり、十時三十分、呼吸がとまり遂に亡くなった。
と書いてある。
そのとき一歳半の私は、どこでどうしてどんな表情をしていたのであろう。
祖母は、母が亡くなって数日間、まだ乳離れしない赤子の私をかき抱いて、
「母のない子にしてしまった」
と 、自分のせいのように嘆き悲しんでいたと叔母が話してくれた。
母の病は当時、肺病と言われ伝染病であり不治の病であった。幼子に移ってはいけないと、私が母のそばに行くことは厳しく禁じられた。母は赤子に心を残しながら、一人寂しく二階の奥の部屋に寝ていた。
事情を知る由もない幼い私は、よちよち歩いて行ってはそっと襖を開けて、怖いものでも見るようにちょっと覗いて、
「ひろこ、ひろこ」
と呼ぶ母のか細い声を聞いては、ぴしゃりと大きな音をさせて襖を閉めたという。
「薄情な子だねえ」
と、母は寂しそうに笑ったことであろう。
私はその頃のことを思うたびに泣かずにはいられない。
一年半の幼子に腹を立てる訳にもいかないが、我が子との別れが迫っている母親は、とにかく我が手に我が子を抱き寄せたかったにちがいない。
「この世での縁薄いひろ子。少しでも多く我が乳を吸うがよい。少しでも長く我が手のぬくもりを感じるがよい」
きっと母はそう言って私を抱き寄せたかったことだろう。
だがそれは許されることなく、幼子のそっけなさに泣き暮れることしかできない母であった。
「ひろ子が冷たい子なんじゃないなぁ。ひろ子には、暗い奥の間に青白い顔をして寝ている母さんが、なんとなく他人に思えたんじゃなあ」
祖母は夜なべ仕事の仕立て物をしながら、そんなふうに話してくれた。幼くして母を
亡くしいた私を哀れに思ったのか、一方ならぬ愛情をもって私を育てた。
祖母は七人の子を育てたが、八人目の子を授かったようにして私を育てた。私は六歳になるまで祖母に可愛がられ育った。
それでも三、四歳の頃は毎夜の夜泣きにほとほと困ったこともあったようだ。
「この子は母さんを思い出して泣くのだねぇ。こんなに切なそうに泣くのだもの」
と、私がしゃくり上げて泣く姿を見ながら一緒に住んでいた叔母と二人、一睡もできないこともあったという。
私が六歳のとき、新しい母がきた。
私は新しい母が来た日のことを全く覚えていない。どんな風に新しい母が私に挨拶をしたのか、誰が私に新しい母を紹介したのか、全く記憶にないのだ。
私の記憶は、その一年後の事から鮮明になる。
その日は私が小学校に入学する日であった。花模様の着物を着て、花模様の草履を履き私の手を引いて母は入学式に出席した。美人の母に手を引かれ、誇らしげな思いで胸を膨らませて歩いた校舎までの道はまぶしい花道だった。
「おかあさんと一緒でいいねえ」
と途中で出会った人が口々に言ったのも、今から思えば意図のある言葉であったのだ。
それからの母は私を第一に考えるように、父兄会といえば必ず出席し、学校から帰る私をいつも笑顔で迎えてくれた。
ぽっちゃりと赤ら顔の私と違って、色白で細面の美人の母は私の自慢の母であった。
この母は私を産んだ母なのだと、ことあるごとに思い、自分に納得させようと意識的に思っていたのは不思議なことである。
小学校が国民学校となった太平洋戦争の真っただ中、私は五年生になっていた。
雪の降りしきる冬に母は学校に弁当を持ってきてくれた。
かすかな音をたて教室の戸が開き、床を滑って弁当が私の足元に来た。私は慌てて辺りを見回した。母の姿はなく、他の生徒が気がつくこともなかったが、私はきっと母が届けてくれたのだと確信していた。朝食が粥やふかしいもの時は弁当が作れないのだ。私は温かい芋御飯を、とくに母に感謝もせず食べた。
女学校に入学して間もないある日、豊美村から通学していた同じクラスの友人から、母が私の本当の母でないことを知らされた。
「あんたのお母さんは継母がだで」
と言って私をじっと見つめたと友の顔を思い出す。ただ私はあのときかなり冷静であった。ああ、やっぱりそうだったのか。私を産んでくるた人ではなかったのが。やっぱり、というのが当時の私の正直な気持ちだった。
なぜ、やっぱりという気持ちになったのか分からないが、私の下に妹や弟が生まれてから、なんとなく感じることがある直感だった。
その時は、ただはやくおばあちゃんにこの話をしたいと思い、走るようにして家に帰った。私の話を聞いた祖母は
「下段(豊美村)の親戚がしゃべったのだな」
と言って怒りを露にした。
「おばあちゃん、ええで、、私は分かっていたから。あの子が悪いのではないで」
と私は私に話した友を庇って言った。
美人の母はやはり私の生母ではなかったのだ、と思うと私は残念な気持ちと、
私のまわりにこれまで薄いベールのように揺らいでいた靄が払拭されたような透明感もわき、ゆるやかに心の中をめぐるちいさなショックを感じていた。
母が継母を脱党してからの私は、お母ちゃんと今まで通り呼びながらも、どうしても飛び越え割れない溝を作ってしまう。
継母は次々と生まれるわが子に手がかかり、私は祖母の目の中に飛び込んでしまった。
継母は随分と私に気を使ってくれていたが、祖母が私にだけ注ぐ愛情と、六年間祖母だけによって育てられた私の間に入り込む余地がなかったようだ。常に、遠慮という心模様が織られていたのを子供心に私は感じてきた。
私はひとりだけ違うのだという僻みと、居場所のないはみ出しっこなのだという心を抱えて、波乱の思春期と青春の日々を過ごした。
その母が、二十数年前、あっけなく五十八歳の生涯を閉じた。 暑い夏の朝だった。
私は結婚して二人の子の母になっていた。病院に駆けつけた時は、すでに継母の呼吸は止まっていた。父の次に死に水をとらせてもらったが、万感がこみ上げてきて、ただ「ありがとう」とだけいった。
母の実子が五人もいる中で私が真っ先に死に水をとることができたのは、異母きようだいたちの気遣いもあったのだろうが、父の変わらぬ心があったと思う。その父の心は母にも生き続けてきた。
若い頃の私の目に余る行為を、父も母も許し続けた。母は声を荒らげたこともなかった。六人の子供の長女として扱い、いつも世間の嵐の盾となり、父との潤滑油となり実子たちには私を姉として慕わせてきた。
私が二人の子の母となって思ったことは、自分にはできそうもない母の献身だった。
窓つたうひねもすの雨淋しかり
母終の日の点滴に似て
私は母への気持ちを短歌にした。母の死後雨の日が続き私は母の病室で見ていた点滴のしずくを思い出して泣いた。
私は生母のことをよく覚えていない。面影も、何の記憶もないのである。
たった一枚の赤茶けた写真。その写真が私と生母を繋ぐたった一本の糸だった。
波型模様の着物を着た母は、帯にかぶさるように膨らんだ胸元をしている。私に乳房を含ませていた頃の写真であろうか。
私はこの写真を繰り返し繰り返し見つめたことがあった。
私の母はこの人なのか。この人のお腹から私は生まれたのであろうか。人は自分が生まれる時のことを知る由もない。ただ、物心ついた時、いつも側にいて言葉をかけ、空腹を満たしてくれた人が大切な人なのだ。そしてその人が美しく優しく優しければ、もう、離れることのできない存在になる。
ただ、私は生母の写真を見ながら、母に話しかける。
「私も一歳半になる娘を持ちました。この子のどんな仕草も可愛くて、それこそ目に入れても痛くないほどです。こんな可愛い子を残して死ぬなんて、私には考えられませんあなたはどんなに悲しんで先立たれたことでしょう。たった一度抱きしめたいという願いもかなわず別れていく辛さは思いに余ります」
一児の母となり、私は生母の無念さを理解して泣きやむことができなかった。
「母」という言葉はやはり私にとっては「切ない」言葉なのだ。切なすぎるんのだ。
私が母となってからも、お母ちゃんと呼び続けた母。一枚の写真の中から、数々の思いを送り続ける母。私には二人とも、切ない胸の中に住む母なのだ。
生母のことを恋しいと思うとき、その姿はゆらゆらとして消えてしまい、雲をつかむような母なのだが、私の人生途上で、常に探し求めた生母の愛。
私が愛を探し求めているあいだ、気苦労という癒えることのない拾い物をしてしまった継母。
びんつけの匂い無性に恋ており
生母の遺品の紅かんざしに
紅葉の形をした珊瑚の紅かんざしと、かのこ絞りの赤い布切れの髪飾りに、なんど鼻をすりつけたことだろう。生母の何かを感じるために。
だが、もう髪つけ油の匂いを嗅ぐのはやめにしよう。
秋分の日に、二人の母が眠る墓に参った。枯れ葉を乗せて静かに立っている母の碑に、万感の思いを打ち明けて手を合わせた。
「まだまだ私の苦労は続くわ。おかあちゃんいつまでも見守ってね、また来るから」
と、呼びかけたとき、
「待っているよ」
と、懐かしい母の声が聞こえ、びんつけ油の香りがかすかに漂ったような気がした。