

















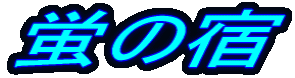
安西果歩
雌蛍の宿る木々はいつ見ても謎めいていて美しい。真っ暗で見えない筈の木や葉の輪郭が、内から光る灯りのせいで浮き上がって見える。
かすかな空気の流れの中で、木々はみなひっそりとして、その中に宿る蛍たちが心置きなく愛し合えるように、身を潜めているようだ。
志乃が蛍の宿が立ち並ぶこのような川辺りを訪れるようになって三年になる。
初めてこの光景を見たとき、志乃は驚き、なぜか、この川辺の宿のことは誰にも話してはいけないことのように思った。それは四十六歳になる志乃がこれまでに見たことのない蛍の謎の世界であった。
六月になると、夏の始まりを知らせるかのように蛍が窓辺を飛ぶことがある。志乃が子どもの頃は近くの川に沢山の蛍が飛び交い珍しいものではなかったが、光をつけたり消したりして蛍は飛ぶものだと思っていた。この川辺の蛍のように木の葉の陰に宿をつくり雌蛍が雄蛍を呼び込む世界があることは知らなかった。飛び回って宿を探しているのは雄蛍だけなのだ。
「雌は灯りをともして待っているだけなのです。でも、ただ待っているのではなくて、光の波長を変えたり、その色も匂いもさまざまなのです。雌も努力をします」
と、その日男は面白そうに言った。
「稀なことですが、雌蛍も飛び出しますよ」
男は意味ありげに言った。ここは見慣れてみると、蛍の光で白い男の顔が浮き上がって見えた。
その時志乃は同僚たちと東京郊外にある鉱泉宿にいた。
蛍を養殖している宿で、宿泊客たちに蛍狩りをさせていた。
志乃は現在中学校の教師をしている。独身の身軽さをあてにされて婦人部の一泊旅行を企画することになり、子連れにも喜ばれるこの宿を選んだのだった。
一行が賑やかに蛍狩りをしているところを、ひとり離れて見ていた志乃に男が声をかけた。
「養殖ではない自然の蛍が変わった世界をつくっているのです。
見に行きませんか。ご案内しましょう」
男は鉱泉宿の主人であった。この宿に決める際、下見に二度ほど来ていてこの男のことは見知っていた。
男は志乃を車に乗せると、暗い農道を慣れた様子で走った。十分ほど走ったところで男は車を止め、
「ほら、ここなんです」
と、志乃に車から降りるよう促した。
男は志乃の手を取り、暗い道を歩き始めた。目が慣れてくるとそこは川辺りの道だと分かった。
突然男の足が止まり志乃の背を押して体の向きを変えた。志乃はよろめきながら向きを変え、目を見張った。思いがけない明るい光景だった。蛍の光がこんなにも明るいものだったとは。
志乃は大きく見開いた目をゆっくりと左右に動かした。
蛍の宿から放たれる灯りであった。
強く弱く、きっと光の波長が違うのだろう。赤く青く、黄みをおび。
その美しさと神秘さは例えようがない。志乃は言葉を失ったまま幻想の世界に立ちすくんでいた。
「ほれ、とれた。帰り蛍だ」
近くで闇が動き男の声がした。
ちょうどその時、幻想の世界に立ちすくみながら、志乃の心の中に戦慄が生まれていた。奇妙な光が志乃の心を射るようにぶつかってきていたのだ。
志乃は男の声とするどい光に脅かされて、飛び上がって男を見た。男は白い顔で志乃を見ていた。
「ほら、手を出してください」
と言って志乃の腕を掴み、開かせた手の中に蛍を入れて包み込むように指を覆った。志乃の手が蛍の光で透けて見えた。
「よく似合う。やはりあなたは蛍の似合うひとだった。蛍のようなひとなのですねえ」
男の声は透明で頼りなく、どこから聞こえてくるのか分からないような声だった。その時の志乃には言葉の意味を考えるゆとりはなかった。ただ、蛍のようなひとという言葉だけが記憶に残った。
「それは雄蛍ですよ」
「分かるのですか」
「あなたの手の中に飛び込んだから」
そう言って男はフフと笑った。
「え、ほんとうに」
「冗談ですよ。飛んできたから雄蛍なのです。雌蛍は飛ばないと言ったでしょう。でも、男を探しに宿を飛び出す蛍も時にはいますよ」
「では、あの木や葉の茂みの中で光っているのは皆雌蛍ですか」
「そうです。蛍は通い夫なのです。源氏物語の世界ですね。そうそう源氏蛍と平家蛍がいますが、同種の蛍が交尾するので、源氏の雌が平家の雄を誘うことはありません」
「それで、光や色が違うのですね」
「ところが外国には雌蛍が同種の雄だけでは満足せず、匂いや波長を真似て違う種類の雄を騙して呼び込むことがあるのです。おまけに、交尾が終わるとその雄を食べてしまうのですからね。
雌とは恐ろしい動物です」
男は顔を背けるようにして話している。が、男の視線を追った志乃はその先にある光を見て身震いがした。男はあの奇妙な光を放つ宿を見つめていたのだ。
「やめて。もう止めてください。私、帰ります」
志乃の声は震えていた。
鉱泉宿に戻る車の中で志乃は言った。
「一晩に何匹もの雄が一匹の雌のもとに通うのでしょうか。雄をつぎつぎに受け入れて、その後の雌はどうなるのでしょうか」
「さあ、どうなるのでしょうかね。よかったら、明日の朝もういちどここへ来てみませんか」
「いえ、けっこうです。光を消した蛍など見たくはありません。茶色に角ばったただの虫ではありませんか」
志乃は神秘的な蛍ではなく醜い現実の姿を思い浮かべていた。
「外国では蛍は害虫だからと嫌う国が多いそうです。蛍は雑食ですから、大切な植物や微生物を食べてしまうのでしょう。もう四、五日してから来てみてください。雌蛍の終焉が見られますから。見た方が気が楽になりますよ」
男は熱心に志乃を誘った。
翌週、志乃は一人で宿を予約した。
土曜日の夜、志乃は鉱泉宿の主人と川辺の宿を訪ねた。そして再びあの奇妙な緋色の光を見た。
「いや。嫌いだわ、あの光」
志乃は激しく言って顔を背けた。
「どうしました。何かありましたか」
男は透き通った声で言って、志乃の肩を抱いた。
「目が慣れるとここは別世界です。明るいのです。なんでもよく見えます。醜いことも、見たくないものも」
言いながら男は志乃の背中を微かに撫でた。男の透明な声に包み込まれるように志乃は癒されていった。
「明日は楽しいところに案内しましょう。今夜はゆっくり休んでください」
男と別れて志乃は部屋に戻った。ひとりになってあの緋色の光は何を伝えているのかを考えた。だが、その光は思い出したくないものの暗示なのかもしれない。考えるとまもなく志乃の思考は混乱し、職場での出来事ばかり浮かんできた。
「もう、お休みですか。熱いお茶をお持ちしましたが。さっきお元気がなかったようなので。よろしいですか」
男の声がして、襖が細めに開けられた。
「ありがとうございます。ご心配かけましたか。なんでもありませんから」
志乃の声で男は襖を大きくあけ、お茶の盆を持って座ったまま膝でにじり入ってきた。
その仕種が動に入っていて志乃は不思議な気がした。この男は何者なのだろう。ただの鉱泉宿の主人なのだろうか。ここは東京といっても、ほんの数年前まで電気が通っていなかったところだ。中曽根総理の頃開発が進んだ地域なのだ。
しかし、男が差し出したお茶を一口飲むと志乃はほっとした。目を閉じてさらに一口味わい、
「おいしい。生き返るようです。有難うございました」
と礼を言い、男の顔を初めて正面から見つめた。
年の頃は六十歳を少し越えた頃であろうか。色は白いが彫りの深い顔である。鼻が少し先の方で曲がっている。そのせいで、老けて見えるのかもしれない。男の妻がこの宿の女将をしているのだが、五十歳前後に見える。志乃にはこの夫婦がなぜかそぐわないように思える。男の上品さに比べ女将には暗い翳が見え美しさは感じられない。
「志乃さんでしたな。あなたは神経の細い人ですねえ。中学校の先生には思えませんよ。まだ若い」
男は目を細めて志乃をみている。
「明日はね、良いところへ案内しますよ。登り釜がある陶芸家のところです。空壺焼きでしてな、昔このあたりにあったのですが、しばらく途絶えていて、幻の空壺焼といわれていました。ところが二年ほど前にこの空壺焼を始めた人がいるのです。京都で修行された人でして、空壺と縁のある人のようです」
志乃は男の話につられてしまったが、いつのまにか明日も男と付き合うことになってしまったことに、なにか腑に落ちぬものを感じた。しかし、志乃も陶器は嫌いではない。二十数年も前には新進陶芸家の作品集を手がけたことがある。大学を卒業して間のないころだった。
そこまで思い出したとき、志乃は背中に氷の棒がするりと滑り落ちるような冷たさを感じて声をあげそうになった。
「何かありましたかな。顔の色が良くないようですが」
男は志乃の変化を見逃さず心配そうに言った。
「思い出したことがあります。明日のお誘いはお断りしなければなりません」
「そんな。空壺に関係がありますか。空壺とは関係ないのでしたらぜひ行ってください。お願いします」
男の真剣な表情に、志乃は迷った。
「では、明日の朝に決めてはいけませんか。今夜冷静に考えてみますから」
男は「そうですか」と言いながら引き下がったが最後まで強い未練が顔に残っていた。
陶磁器、陶芸家。それにまつわる思い出は志乃にとって二度と思い出したくないことだったのだ。
二十年前の辛く口惜しい思いがいきなり志乃の全身を覆った。
ひとりきりになった静かな部屋で、志乃は頭から座布団を被って身悶えた。
「ああ、ああ、ああ」
その声しか口を出る音はなかった。涙など出てはこない。
数分後、志乃は上半身を起こして髪の乱れを掻き揚げた。
二十年以上強く封印をしてきた事がたった今溶かれてしまったのだ。幾重にも氷の板を張り巡らして心の底に閉じ込めたものが、あの宿の主によって暴きだされてしまった。
あの男、橘公彦が志乃を騙したのは志乃が大学を卒業した年だった。正確に言えばその時はまだ騙されたとは思っていなかった。初めに就職をした出版会社で、半年もたたないうちに志乃は新進陶芸家橘公彦の作品集を編集することになった。作品は茶道具が多く、茶道が華やかな時代で、とにかく大変な仕事であった。登り窯は鳥取県大山の麓にあり、数人の弟子たちが預かっていた。その地にはあまり良い土がないとかで、橘は素材の土を求めてあちこちへ旅をした。そんな時にも志乃がおともをすることがあった。
当時橘は四十五歳で志乃にとっては、住む世界の違う人という存在であった。
にもかかわらず、志乃は二十四歳の時橘の子を生んでしまった。初めての男で、若い編集者にとっては、憧れの人からのお手つきであった。
子を生む直前になって、実家には妻があり子どもはいないが
才能ある陶芸師であることが分かった。
「頼みます。子どもを生んだら橘の子として私達にいただきたい。鳥取の方で育てさせて下さい」
と橘は言った。このとき志乃は初めて最初から騙されていたのだということが分かった。
志乃は慌てて全てを捨てて群馬県に住む友人を頼り逃げた。
そこで子を生み育て始めたのだが、間もなく志乃は結核に感染していることを医者から知らされ、完治するまで子どもと離れることを余儀なくされたのだった。
志乃の実家はとうてい受け入れる筈がなかった。まだまだ世にでたばかりの女が身ごもっただけでなく、相手が妻のいる男で、志乃の父親とあまり年の差もないことで親戚中の顰蹙をかっていた。母親は、勘当だ、家とは関係のない人間になったと思いなさいと厳しく言ったくらいだ。
橘家はみな喜んでこどもを引き取った。子どもの名は「翔」とつけていた。
ところが、志乃が結核になったのは橘公彦の病気が移ったことが分かり、公彦も奥多摩に登り窯をつくり、そこで仕事を始めた。
志乃は群馬から戻らず、病気が完治するとすぐ、翔を迎えにいったのだが、二歳になっていた翔は、どうしても志乃に近寄らなかった。志乃は小さな手で、近寄る志乃の顔を思い切り押しのける翔の仕種に深く傷ついた。今思えばそれは翔の出来る限りの反発であったのだ。嬉しさのあらわれだったのだが、橘との出会いでことごとく傷ついた志乃にとっては、思いがいたらなかった。
ひとりで戻る山陰線の列車の中で、思い切り、三年分の涙を流し、この三年間の出来事は心の奥底に凍結して忘れきってしまおうと決心した。
それが、二十三年ぶりにここで封印が解けてしまうとは。
志乃はふと、翔のことを考えた。
「翔」
あれ以来初めて口にした言葉だった。
翌日、男の誘いで志乃は登り窯の窯元を訪ねた。
空壺焼の窯元は男とかなり懇意にしているようで、自ら二人を茶室に誘い、茶を点ててもてなした。
「山吹はんとこの古空壺はどうなりました。ほんまもん言うことは分かっていますさかい、いまさら鑑定はいらん思います」
窯元は静かに言った。男は山吹というようだ。何かの号だろうか、と志乃は雅の空間にいるように思った。
「値がついても、手放すものでもありません」
男も窯元の言葉に対して、呟くように言った。
「そうどす。私のも、買う人がおりまへんやろなあ。第一、値がつきまへん」
古空壺とはそんなに貴重なものなのか、見てみたいものだと志乃が思っていた時、
「そうそう、あの茶碗でこのひとに一服たててあげてくださいよ。その為に寄らしてもらったのですよ」
と、男が窯元に頼んだ。窯元は軽く頷くと、いそいそとした足取りで奥の間の方へ行った。
茶碗の入った桐箱を大切そうに持ってあらわれた窯元は、志乃の前に箱を置いて言った。
「これが古空壺どす、この箱を見て下さい。蓋が盛り上がっています。桐材で曲線を描くゆうのは難しいです。私のものと、山吹はんのと同いなのですわ。それで、親しゅうなってしもて」
「古空壺は小堀遠州を真似た透き茶碗です。湯が入れば模様が見えます。客が茶を飲み干せば消えてしまいます。茶を楽しむ
お客さんだけが透けた模様を見ることができるという。まさに茶道の本髄ですかな。茶道とは客のもてなしです」
「もてなしをもてなすいうのもありますなあ。茶というもんは人間同士がどこまで相手に心配りを出来るか、限界までやりますわ」
茶道の作法とはそこのところなのだと、二人の談義は楽しそうに続いた。
志乃は話を聴きながら、白地に薄青磁色で描かれた樹木の象徴画が、茶を飲んでいる間は透けていて、亭主の元へ戻るときには浮き上がった絵になる、不思議な茶碗でゆっくり茶を味わっていた。
「あの茶碗にしても、茶の道にしてもなんですが。志乃さん、私はあなたが陶器のようなひとに思えます。そう、蛍のようなひとにも思えますね」
男は帰りの車の中で言った。
「また会ってください。こんどは奥多摩の蕎麦屋へ案内します。趣のある店ですよ。ぜひ、志乃さんと行きたいのです」
志乃はまた男の頼みを受け入れた。夏の終わりにもう一度会うことを約束したのだった。
その日男と別れた志乃は東大和にある自分のマンションに戻った。近くに実家があり、今では勘当も解け実家に戻る日の方が多いくらいであった。
もうすぐ夏休みになるというのに、梅雨の季節は終わらず、はっきりしない天候が続き部屋の中には蒸し暑い熱気が籠もっていた。志乃は部屋に入るなり窓を開け放し、クーラーを点けて、改めて部屋の中を見渡した。
「彼は私を蛍のようだと言った。では、ここは蛍の宿かしら」
と呟きながら、そういえば雄蛍が三匹になっているではないかと思った。私は三匹の蛍にそれぞれの安らぎと寛ぎを与えているではないか。飛んできては出て行く蛍たち。私は見返りなど考えたこともない。まして、食い殺してしまうなどもってのほかだ。それどころか、英気を養った蛍たちは元気に飛び出していく。
一匹目の蛍は志乃が二十六歳のときにやってきた。彼は三十一歳で信介と言った。十八歳で結婚した同い年の女房に辟易としていた。三人の子育てと零細事業のやりくりで疲れていた。
中学校に通った覚えはない。農家の九人兄弟の末っ子だった。
学歴のない人間は自営をするしかなかった。妻も無力だった。戦後の社会で極道が盛りであった。その道に首を突っ込まないように親達が二人を結婚させたのだ。
なんとか貯めこんで家を建てようと思った材木を貰い火で焼失してしまった。それでも這い上がりクリーニング屋を始めた信介は、教師になったばかりの志乃と出会い、さっそく志乃に子ども達の家庭教師を頼んだ。小学校の先生しか知らない彼にとって、中学校の女教師は憧れの人であったのだ。
しばらくして信介が診断のつかない病にかかり、見舞いに行ったとき二人は病院の深い林の中で結ばれた。
それ以来二人は週末を一緒に過ごすようになった。週末の父親を子ども達から奪ったことに、志乃は心を痛め続けてきた。
ある日三人の子どもが揃ってマンションにやってきた。
「今日はおかあさんの誕生日なのです。おとうさんにすぐ帰るように言ってください」
と、玄関に出た志乃に長女が言った。
「はいはい、すぐ帰るわね。おとうさんはちょっと休んでいるのよ。いま帰るわね」
信介は子ども達と連れ立って帰っていった。
次の週、信介の女房が子ども達とマンションへきた。
女房は三人の子ども達の背を押してふたりの前に突き出して言った。
「あんたたち、心中をしようとしているそうね。そんなことしたら、私も子ども達を道連れに死んでやるからね」
女房の覚悟を知ってしまったふたりは迂闊な行動ができなくなってしまった。それから、いくつもの修羅場があった。どんな修羅場でも、信介は志乃を諦めなかった。志乃は信介にとって夢であったのだ。これまでの夢のない現実に見つけたたったひとつの夢だったのだ。女房も諦めたのか、ふたりは公認のような中で過ごしてきた。
その時志乃はむしょうに信介に逢いたくなった。だが、志乃から電話をかけることはしなかった。朝まで待つしかないのだ。
次の日信介からモーニングコールがきた。
「昨日、とても会いたかったのに。午後は帰っていたのよ」
と、志乃は甘えた。
「そうか、そうか。ごめんね。一泊旅行というから夜まで戻らないとおもったのだ。きょうは行くから」
信介はいつものように志乃の甘えに応えて優しく言った。
その日の夜、ふたりが夕食を済ませた時、
「おまえ、髪の毛が気になるなあ。少しカットしようか」
と、信介は志乃を浴室に誘った。いつも志乃の髪の毛は信介がカットしていた。夏は短めのマッシュルームカットで、冬は長めに肩のところで揃える。どちらも子どもっぽいスタイルである。末っ子の信介は妹分だと思って志乃に接する。
「志乃は癖毛だから、パーマ代がいらなくていいなあ。きょうは短めにカットするぞ。また、プール指導だとかクラブ活動だとかで、しょっちゅう洗うだろうからな」
信介は言いながら鋏みを起用に動かしている。ふたりとも丸裸である。
「ほら、じっとしてろよ。あまり陽にやいているとシミになってしまうよ」
志乃の髪に櫛を入れながら、こどもを諭すように言う。志乃は父親に言われている幼女のように、はい、とか、分かったとか頷くのだった。
翌日、志乃はさっぱりした髪で登校した。
誰もいない職員室に入り、ガスに大きなヤカンをかけ、窓を開け放し終わると自分の席にハンドバッグを置き、反対側の裕一の席に行く。彼の机の上にあるレターボックスから、こげ茶色の小さなメモ帳を取り出すのだ。そこには必ず裕一からのメッセージがある。
『今週は水曜日にかみさんがいないので、火曜日に行きたいのですが。その方がゆっくりできます。あなたの好きな寿司を買っていきますね』
と書いてあった。
二匹目の蛍である。彼とは十年前からの付き合いである。二歳年上だから四十八歳である。生活指導主任をしていて、同じ指導部にいる志乃とは一緒に遅くまで仕事をすることも多い。
十年前、夏の暑い日だった。プール指導にあたっていた裕一が日射病で倒れた。その日日直であった志乃が救急車を呼んで病院に運んで、彼の妻に連絡を取ったが、妻は子ども達をつれて京都の実家に帰っていた。
「迂闊なんですよ。生徒をみている教師が倒れるなんて。私はこちらへ来たばかりで戻れませんから先生申し訳ありませんが見てやってください」
と言われた志乃は、入院の手続きやら必要な衣類等を揃えて、おまけに看病まですることになった。網膜剥離を起こしそうな病状だということだったのだ。
退院して二学期が始まる前の日、裕一の妻から電話がきた。
「主人は失明するかもしれないのです。でも、勤めには電車に乗ってでも行くといいます。私は主人が途中で飛び込み自殺でもするのではないかと心配です。先生はちょっとまわりみちをして主人を乗せていっていただけませんか」
という話だった。
そんなわけで、九月から一月まで、二人は一緒に通勤した。
来月から運転しても大丈夫だということになり、裕一はひとりで通勤するという前日のことだった。
「志乃先生、明日の朝、僕のレターボックスの一番したを開けて見てください。あなたへの手紙が入っていますから読んでくださいね」
と、裕一が言った。
翌朝、引き出しを開けた志乃は白い二通の封筒をみつけた。
一通の表には『遺言』と書かれていた。志乃は驚いた。なんとなく裕一の態度がおかしいとは感じていたが「やはり」という思いがした。そう意識をすると、封筒を開く手に震えがついた。あせる気持ちで中の紙を引き出して目を走らせた。
『もし、自分にもしものことがあったなら、原沢志乃先生に河野裕一の財産はすべて贈るものとする。それは、私の命を永らえさせてくれたことへの謝礼である』
と書かれていた。
もう一通の方は、遺言は預かっていて欲しいということと、生きている限りあなたと暮らしたいと書いてあった。
読み終わった志乃は手紙をもとのレターケースに戻しておいた。夕方裕一からマンションに電話がかかった。
「志乃先生。僕のこと変な男と思いましたか。気味が悪かったのでしょうか。いきなりあんな物を渡そうとしたのですからね」
志乃は黙っていた。どう応えてよいのか分からなかった。
「あの、でも、もう一緒に通勤できなくなるし、これまでのお礼をどう表したらいいのか。僕は、感謝してもしきれない思いなのです」
「たいしたことではないのです。私も途中が退屈しないですみました」
「そんな。あの、僕、これからそっちへ行ってもいいでしょうか。どうしても、これ、持っていて欲しいのです」
裕一はそう言って電話を切り、しばらくして志乃を訪ねてきた。
「財産といってもね、僕の取り分だけなんですよ。生命保険の受け取りとか、クラシックレコードとか、田舎の家にあった僕だけの宝物です。保険は受取人をあなたにしました」
裕一はそう言いながら、自分の命を救ったのは志乃であり、妻は裕一が死ねばよいと考えたに違いないと言った。
公立小学校の養護教諭をしている裕一の妻は、二人の子供たちは愛しているが、夫に愛情はもてなくなっているというのだ。
「そんなこと。だって、子どもは育てるのですもの、十分の愛情を注ぐわよ。あなたに対しては違った愛情があるのではないかしら。同じようにされないからってそんなふうに思うのはいけないわ」
「結婚とか家庭とかに夢を持つことが甘いのかもしれません」
妻は徹底した男女平等論者で、家庭、家族に関わる全てが平等に計算されていた。仕事も経済も、全て折半だったのだ。
子どもができてからはセックスにもその考えが導入され、彼の求めになかなか同意しなかった。それでも夫が求めると、
「あなた、大丈夫?できるの?時間がかかるのはいやよ」
と前置きがあり、裕一は力なく終わりになるのだった。そんな日の翌日はさっそく妻の姉がマムシドリンクを持って現れることになるのだと裕一は話した。
そんな秘密の出来事まで打ち明ける裕一に志乃は同情した。それから十年の月日がたっている。
翌日、火曜日の夕方、クラブ活動を早めに終わりマンションに帰った志乃は、いそいで窓を開け放しクーラーをつけた。ここは三階なので太陽の日はあまり影響がないのだが、一日中閉め切ったコンクリートの部屋は昼間の暑さが残ってしまい、気温は三十度を越えている。クーラーをつけてもしばらくは窓を開け放している。そうしたまま志乃は浴室に行きシャワーを浴びて出てから窓を閉める。
さっぱりした気持ちで志乃はキッチンに立ち、吸い物を作り始める。だしをとり、湯葉と三つ葉の具を揃えた時チャイムが鳴った。志乃は料理を続けながら裕一が入ってくるのを背中で感じていた。裕一はチャイムを鳴らしても志乃が出て行かないと、こそっという音をさせて鍵を開け、静かに入ってくるのである。
「今日は早かったのですね」
裕一は小さな声で言って、買い物包みをテーブルの上に置いた。
「おかえりなさい。シャワーをどうぞ」
志乃の背後からそっと肩を抱く裕一に、前を向いたまま志乃は言う。
「じゃあ」
と、また小さく言って浴室に向かう裕一の背中をわずかに見て、志乃はテーブルに置かれた包みを開く。中から寿司を取り出し寿司板に並べる。奈良漬と京菜の漬物を小鉢に盛り付けてから、買い物のビニール袋に残されたビールを取り出し冷蔵庫に入れる。裕一は志乃がビールも酒も飲めないので、一缶だけビールを買ってくるのである。
「さっぱりしました。生き返るようですね」
裕一は言いながら椅子に腰を下ろすと、志乃が注いだビールを美味そうに飲んだ。
「ひらめのエンガワとあなごはあなたの分ですからね。きょうはあなごのタレをたくさんつけてもらいましたから」
先週はあなごのタレが少なくて、志乃が残してしまったので、裕一はそのことを言いながら寿司を勧めた。
裕一は学校で生活指導をするときの、かなり強気な面は身体の裡の方におさめ、言葉遣いも声も過ぎるほど優しい。その動作は密やかでさえある。
「志乃さんの吸い物はいつご馳走になってもおいしいですねえ。コツはなんですか」
裕一は吸い物が好物だった。同じことをよく言う。
「そうね、だしをしっかりとることと、あとは、あとは企業秘密よ」
志乃は少し意地悪く言う。料理を短時間で美味しく作ることが彼女の密かな自慢であった。
「ああ、そうそう、津軽三味線のテープを録ってきましたよ。演奏会の録音だからあまりきれいに録れていませんけれど」
食事が終わった頃裕一はテープを取り出してデッキにセットをした。
三味線の音がいきなり、震えるような音色で志乃の耳に伝わってきた。素朴で力強く、したたかに地の底から這い上がってくるような、暗い響きだった。心に戦慄を呼び起こすような津軽三味線の音は、雪国の痩せた町並みを想像させる。そこでは、三味線も、村も町も、人々の心も震えていた。
志乃は体の中を、何度か、突き抜けていくような戦慄に酔いながら、椅子の中に吸い込まれていくような感覚を楽しんでいた。
そのとき、三味線の音が消え、気がつくと裕一が志乃の横にきて肩を抱いていた。彼はそのまま志乃を椅子から立たせると、ベッドルームへ誘っていく。裕一の熱っぽい息が志乃の頬をくすぐる。
「まあ、もうこんなに大きな影が・・・」
部屋へ入ったようすに目をあけ、志乃は部屋の中を見回すようにして言った。
そこにはさっき点けたランプがかもしだす不思議な世界が作り出されていた。それは、幾筋もの光が差し込む水槽の中のような、或いは木漏れ日で霞んだ森の中にいるような、柔らかく暖かい、のびのびとした世界であった。
このランプは志乃がニューギニアへ行ったとき見つけて買ってきたものだが、丸い椰子の実を繰り抜いて作られていた。全面にすかし彫りの絵がほどこされていて、中に取り付けられた電球が強く光ったり弱くなったりして、時間がたつにつれて天井や壁に大きな影を作り出す。いまは、部屋いっぱいに大きな影絵を作り出している。その中にあるベッドに横たわった二人は、水槽の中の金魚となり、或いは森の小さな動物となって、泳ぎ戯れ、やがて快い疲れを感じながら軽い眠りにつくのである。しばらくして
「ごめんね。また、ひとりにしてしまうんだね」
と、小さく声をかけると裕一はベッドを抜け出し服をつけ始める。時間なのだ。
「そのまま眠っていてね。おやすみ」
身繕いを終えた裕一は志乃の額に軽く唇をつけ、再びこそっと音をたててドアーの鍵を掛け、足音を忍ばせて階段を下りていく。今夜も、十一時過ぎに終わる塾へ娘を迎えに行くのだ。
志乃はベッドを下りると、窓のカーテンを細く開け、駐車場へ向かう裕一の後姿を見送る。じっと見つめる志乃の目から涙が徐々に溢れてながれ落ちる。
その次の日だった。
勤めから戻り、室内で鳴っている電話の音に心急かれながら部屋に駆け込み受話器を取ると、哲郎の声が聞こえてきたのだ。
三匹目の蛍であった。
「お帰りなさい。やっと捕まりましたね」
志乃は一週間ほど前に哲郎と久し振りに出会っていた。
「ずいぶん忙しい人ですねえ。何回電話したと思いますか。今もね、あなたの実家に電話して、志乃ちゃんがたった今実家を出たっていうことが分かったのですよ」
哲郎の話し方はかなり酔っているようである。
「まあ、そう。ごめんなさい。私ね、秒きざみで生きてる人間なの。それで、今夜はどうしたの」
「実家のおかあさん、あいかわらずだねえ。僕のことが分かったら、あーら、いきてたの、だって」
「まあ、母ったら、失礼な事言うのね。他人事だと思って。かんたんに死なせないでよねえ」
「いいの、いいの。おかあさんって優しいよ。志乃ちゃんは今帰ったばかりよ。もう少ししてから電話した方がいいわ、だって。電話番号まで教えてくれたよ。僕はとっくに知っているのにね」
と、哲郎は楽しそうに話した。
「それで、何かごよう?」
「冷たいこというのね。声が聴きたくて電話したんじゃないの。
じつは今、マンションの下の電話ボックスでかけているんだ。ケーキも買ってきたし、おじゃましてもいいでしょ」
志乃は慌てて外を見た。すぐ近くのボックスに人影が見える。
「なあんだ。いるの。それでは少しだけね」
受話器を置いて志乃が服を着替える間もなくチャイムが鳴った。ドアーを開けると、神妙な顔をした哲郎が立っていた。酒の匂いがした。
「リッチな部屋ねえ。志乃ちゃん、優雅に暮らしているんだね」
哲郎は部屋へ入るなり言った。
「おかげさまで。あなたと一緒にならなかったからよ」
「それはご挨拶だなあ。でも、正解かもね。ところで、この間はありがとうね。ほんとに嬉かった」
哲郎は二週間前のある日、志乃に車で送ってもらったことがあったのだ。
その時は夜遅く志乃が実家から戻る途中で偶然見かけたのだった。車のヘッドライトに照らし出されたのは、ボロクズのように体をまるめて転がっている人の姿であった。よくみると、転がっているのではなく電柱にもたれているのだが、顔を伏せているので丸められた服のように思えた。志乃はライトを向けたまま近づいていった。
それは酒の匂いをさせた男であった。志乃が覗き込むと男は顔をあげて志乃を見た。
「あら、哲郎さん?どうしたの、こんなところで寝ちゃったの」
志乃はそれがかつての恋人であった哲郎なのに驚いた。
「いえいえ、けっして眠っているのではありませんよ。駅からタクシーに乗ってね、気分悪くなったから『吐くぞ』って言ったらこんなところで下ろされちゃったんだよ。あの、くもすけ野郎め」
哲郎はぶつぶつと毒ずいている。
「ねえ、哲郎さんなのでしょう。あたし、志乃ちゃんよ。分かる?覚えていないのでしょうねえ」
「え、志乃ちゃん。ああ、志乃ちゃんね。知ってる、知ってる。
映画みたねえ。いい車に乗っちゃって」
「なんだ、分かるのね。さあ、送っていくから車に乗ってよ」
志乃は哲郎の住んでいる所を知っていた。彼が妻や子と別れてたった一人で神社の社務所に住んでいることも、その社務所が朽ち果てた建物で歩くことも難しいのではないかと思うくらいであることも。彼はそこで正月だけの神主をしていた。
「嬉しかったんだよ。志乃ちゃんが僕だと分かっても乗せてくれたんだもの。すごい家だろう。驚いたかい」
「あたしはお正月のたびにあの神社にはお参りに行ってたのですもの。遠くからだけどあなたの顔や姿は見ていたわ。こどもさんが大きくなっているのね」
哲郎は分かれた妻子にいまでも仕送りをしているようだ。近所の噂話で志乃は知っていた。
「仕送りして育てたのですってね」
「子どもたちのことかい。だって、母親が不倫してあげく離婚したんだよ。その上父親までいなくなったら可哀想だろう。縁は切らなかったのさ」
「馬鹿ね。あたしを捨てた罰よ」
買ってきたケーキは志乃が食べている。哲郎は持ってきた一升瓶から茶碗に入れた酒を美味そうに飲んでいる。
「ねえ、今でも分からないのだけれど、あなたはどうして私を捨てたの?とても急だったわよね。あなたが冷たくなったの」
二十五年前のことを志乃はようやく哲郎に言えたのだ。
哲郎は志乃より二つ年上で、近所に住み同じ剣道の道場に通う中だった。道場でも資格でも志乃の方が先輩であったため、志乃はよく哲郎の稽古の世話をした。
二人が大学生であった二年間がふたりの恋愛ごっこの時期であったのだ。
ふたりで新宿や銀座で映画を見たり食事をしたり、本屋をのぞいたりという程度だったが、その頃のふたりにはそれで恋人きどりになれることであったのだ。
まだまだ剣道は花道ではなく、少し遠慮がちにしていたものの、ある大学に道場があると聞いて、志乃は哲郎を誘った。
「渋谷に大勢が稽古している道場があるようなの。ねえ、道場破りしてみない」
志乃は高校三年生だった。大学二年生の哲郎を引き連れて道場破りに出かけたのだ。
だが、稽古場の窓から聞こえる気合のすごさにおじけづいた二人は顔を見合わせて、今降りたバス停から逆周りで帰ってしまった。けっきょくその気合に憧れて志乃はその大学を受験したのだが、四年間は剣道部で通した。
その後、四年間が恋愛時代なのだが、後半の二年間が過ぎナイターを見る事がおおくなったのは、哲郎の勤めが水道橋にあったからだった。哲郎は残業の合間によくポップコーンを買って志乃の前にあらわれた。
「ねえ、あの夜、有楽町で映画を見ての帰りだったわよね。あなたが冷たくなったのは」
酔うこともできないみたいに立て続けに飲む哲郎の横顔を見ながら志乃は言った。
「あの日の映画は『黒いオルフェ』だったわ。見たあとにお寿司を食べたわねえ。そして、電車にのったわ」
「よく覚えているねえ。俺は覚えているよ。だって、志乃ちゃんという女の子とのつきあいを卒業した日なんだよ」
「なによ、それ。けっきょくキスもセックスもしなかったってことなの。それで別れたの」
「あの日、俺、寿司にあたったんだな。途中で腹が痛くて我慢ができなかったんだよ。途中下車したら西武線の終電に間に合わないしさ。志乃ちゃんは隣で居眠りしているし、おれ、千駄ヶ谷で飛び降りたろう。あそこで泊まったのさ」
そうだったのか。それで、大人の恋愛をしたくなり志乃をふったのか。志乃は残念な思いがしたが、今ここにいる酔っ払いの哲郎を見て、運は良かったのではと思った。
四十六歳になっている志乃にはそれだけの話しでも哲郎の気持ちは良く分かる。しかし、あのときの志乃は大学卒業間近の二十一歳だったのだ。昭和三十七年の一月だった。
「あなたも晩生だったのよね。夜の暗い住宅街を歩いているときも、寒くて肩寄せあってもそれ以上にはならなかったわね。野合なんてできなかった」
野合なんて言葉も、哲郎と別れてすぐに結ばれた志乃とは二十歳も年の離れた男からならったものだ。
けっきょく、二年後に哲郎は七歳年下の女性と結婚した。十年目に妻の浮気が本気になり、妻は三人のこどもを連れて別居して十二年になる。籍は抜いていないのだという。
「相手は俺よりずっと年下なんだ。二人でスナックをしているけれど、いつ破綻がくるか分からないしな」
哲郎の酒はもうなくなってきている。哲郎は一升瓶を透かして見ながら、
「今夜はそろそろ終わりかな」
と言った。
「どうするの。送っていきましょうか」
「いえいえ、志乃ちゃんは明日学校でしょう。先に寝てください。俺はここで一眠りして帰りますから。だいじょうぶ、だいじょうぶ。慣れていますから」
哲郎はそう言いながらテーブルに上半身を伏せて眠ってしまった。
翌朝哲郎の姿は見えず
『おはようございます。ありがとうございました。寿命が延びましたよ。また、来さしてくださいね』
とメモを残していた。
蛍が三匹になった。
それから二年がたったのだ。空壺の窯元を訪ねてちょうど三年目になる。
奥多摩の渓谷の際に立つ、思いも寄らぬ洒落たそば処を訪ねたとき男は言った。
「こんな楽しいときがもう一度おとずれようとは思いませんでしたよ。志乃さん、ありがとう」
その店は、入り口からいきなり長い階段を下りて行く、エレベーターがあるくらいだからかなり長い。
「これ、ストリップ階段て言うのです」
男が笑いながら言った。
「下から、降りてくる人のスカートの中が見えるからですか」
志乃は少し幻滅を感じながら言った。
「まあ、そんなスケベ根性もあるのでしょうが。ほら、こんな店の真ん中に下りるのに、まわりがプラスティックで囲まれているでしょう。邪魔にならないのですよ。まるで、店装の一部だ」
「そういえば、ここを降りる人がひとりひとり舞台に登場するみたいですね」
透明なプラスティックの周りには細い金の縁取りがしてある。
さらに、降りたところは多摩川の流れに向かって全面大きなガラス張りになっているのだ。清流の中に立った心地がした。
「すごいお店があったのですね。まったく知らなかった」
志乃は感動して現実ではないような気がした。
そば処を訪ねた日もそれだけで、二人は別々のハイヤーで戻ったのだが、男は頃合いよく志乃をあちこちに誘ってきた。しかし、志乃のマンションを訪ねたいとは決して言わず、蛍が四匹になることはなかった。
男にとって志乃は大切な存在のようだが、志乃にとっても男は宝物であり、男に対してのみ男を感じるという気がしていた。
「ここで、蛍の宿を見るのも三回目になるわ。でも、私、あなたの名前も年も知らない。あなたは私の年をご存知かしら」
今年はあの奇妙な緋色の光を見ても震えがつくこともない。
「年などなんの意味もないことですよ」
男は穏やかな笑みを浮かべながら、きっぱりと言った。
「そうね。私達だって、たった二年間の付き合いなのに、ずっと以前から一緒に暮らしている感じですものね。お互いに、何も知らなくても信じていられるんだわ」
「私はね、他種の蛍の真似をして雄を誘い込む雌蛍を見に行けないことだけが残念なのです。志乃さんと一緒に行きたいですよね」
男は以前他の国の蛍の話をした。
「大きな木に無数の蛍が宿を作ってクリスマスツリーみたいになってしまう木があるのです。そして、同種の雄にあぶれた雌蛍が他種の雌が発する匂いや波長を真似て、その種の雄蛍を呼び込むのですよ。見たくありませんか」
と男が志乃に話したとき、イメージが湧かなかったのだが、図書館で調べてみると、素晴らしい蛍の木があることが分かった。まさに、真夏のクリスマスツリーであった。
「私ね、いつかあなたが話しをされたタイの蛍の木を見に行きたいのです。でも、別々の姓の男女がひとつの部屋に泊まるのも、別々の部屋にするのも嫌ですもの」
「みょうな事に拘るのですね」
男はそう言ってフフと笑った。嬉しそうだった。私を幾つだと思っているのだろう。もう四十九歳になるのに、と志乃は少し気が引けた。
志乃は一度子を生んでいるが、それ以来独身を通していて、住まいは独立しているがいまだに両親の傘の中にいる。そのため年齢よりずっと若くみられる。化粧もしていないしパーマもかけたことがないのだ。男に年齢を間違えられていると思うが本当の年齢を言えずにいた。
人気のない川辺りで男の体が動いた。志乃の肩をそっと抱く。
志乃はかすかに体を震わせたが黙ったままだ。
そうして志乃の肩を抱いたまま男は車の方へ歩いた。志乃には男の手が震えているように思えた。
男はいつものように次の日の約束もしないで部屋まで志乃を送ると、
「おやすみなさい」
とちいさく言って下がっていった。また頃合をみて誘ってくるのだろう、外国へ行く話は途切れている、と思って志乃は眠ってしまった。
翌日、志乃は宿を発つときふと気になって女将に言った。
「ご主人は体の具合でも悪いのでしょうか」
「そんな様子でもみえましたか」
女将は逆に聞き返した。
「もう、としですからね。ずっとまえから悪いのですよ」
それだけを吐き捨てるように言って、勘定をすますとすぐ奥へ行ってしまった。
なんだかそっけない女将の態度に志乃は男が気の毒になった。
男の見送りがないまま家路についた翌日、しつこい電話の音に志乃はベッドから出た。どうせ公彦からの電話だろう。公彦はもう七十歳を過ぎたはずだ。二十六年前に志乃を騙して子を生ませた男である。数日前から電話をかけてくる。息子の翔が精神を病んでいるというのだ。志乃へのトラウムなので一度来て欲しいと言っているのだ。
「どうしたのですか、こんなに早く」
朝の時間は一分でもおしい。志乃は時間の許す限り寝ていたかった。
「こんなに早くでなければ出ないではないか。ますます翔が手に負えん。早く来てくれないか」
「どうして今頃になって私を頼るのですか。あなたがた親子は私を捨てたのですよ。それがどんなに辛く悲しいことだったか、想像ができますか」
志乃は封じてきた封印がはがれて詰め込まれていた言葉が一気に吐き出たようだった。
「それは、何度も謝っているだろう。だが、今は翔のことだけを考えてくれ。わしに対してのどんな思いも受けるから」
公彦の妻は数年前に別れたようだ。翔の病がはっきり分かった頃のことだったという。
「分かったわ。だから、もう、切ります」
志乃は公彦との電話で信介からのモーニングコールを取りそこなったことを口惜しくおもいながら職場に向かった。
だが今日はどうしても運転ののりが悪い。ハンドルのきれが悪いと朝のラッシュには危険である。
志乃は車を路地に入れて止めた。どうしても胸騒ぎが止まらないのだ。志乃は欠席の電話をするために公衆電話を探し駆け寄った。二十数年の勤務の間志乃は欠席をしたことがない。すべてに恵まれていたのだろうが、欠席の知らせを受けた教師は
「どうかなさいましたか。体の具合が悪くなられたのでしょうか」
と心配気にたずねた。
「今、登校の途中なのですけれど、ちょっと急用を思い出したのです。申し訳ありませんが、授業の方のことよろしくお願いしますね」
志乃は咄嗟にそうつくろったのだが、言ってから、たしかに急用があるように思った。それは、あの鉱泉宿の男のことだった。昨日の別れがなんとしても気になった。
志乃は鉱泉宿へ向かった。胸騒ぎはそのせいのように感じられた。
鉱泉宿には一時間ほどで着いた。
「おはようございます」
玄関に立って声をかけながら、少し違った雰囲気を感じた。掃除がしていないのだ。いつもきれいに磨き上げられている入り口全体が汚れて感じる。
「はい」
と奥から走り出てきた女将は「あら」と口ごもっている。見ると女将の姿も全体に乱れてうす汚れて見える。
「あの」
主人に会いたいといおうとして女将の顔をまっすぐに見たとき、志乃の表情は変わった。
「あなたは。あなたは、もしかして」
「主人、たった今病院で死にましたのよ」
志乃の質問をけん制するかのように女将は言った。
「夕べ、救急車で運ばれましてね。今朝、四時二十分でした。先生にお電話でもありましたか」
女将の顔が夜叉に見えた。
「私、すぐ病院へ行かなければならないのです。ああ、でも、ちょっと待って」
再び奥の方へ消えた女将の後姿に目を向けたまま、志乃の頭の中は真っ白になった。
あの女は、あのひとは確かに、公彦の側にいた女だ。女の顔
の焦点がきちんと合って見えた。
信じられない偶然だった。公彦の妻であった女性がここにいたなどとは思いもよらない。そしてその女を私は裏切ろうとしていた。志乃はすばやく玄関を出ようとした。だが、なぜか頭と体が一致しない。
「これですけど。主人があなたに差し上げるようにと言いおいていったものです」
女は無造作に志乃の前に突き出して言った。一目で抹茶茶碗であることが分かった。それも、まぼろしの蛍焼きにちがいなかった。志乃は手をだすことができなかった。
「受け取っていただいてけっこうです。あの人の遺言ですから。
でも、正直に言いますと、これはたいへん高価なものです。値がつかないようなものでしょう。好き者の座興だと思いませんか。あなた、受け取れますか」
言われなくても分かっている。志乃には受け取れない。
「けっこうです。いただきません。私とご主人は、たしかに、ご主人の座興であったでしょう。どうぞ、ご心配なくお宅に置いてください」
女の顔が明るくなった。そして、
「少し待ってくださいね。お渡しするものがあります」
と言いながらいそいそした足取りで奥に消えた。再び手に小さな箱のようなものを持って現れた女は今度は丁寧にその箱を差し出した。
「実はこれもあなたに渡すように頼まれていました。どうぞお持ちください」
志乃は紫の袱紗のようなものに包まれた小さな箱を受け取った。たしかに桐の箱であろう。そして、これも高価なものに違いない。だが、男との思い出に受け取っておこうと思った。
もっと高価な物を受け取らなかったことの心の開放だったかもしれない。受け取ってはいけないものを志乃は受け取ってしまった。
帰りの車は誰がどんな風に運転しているのか分からないまま志乃は走り続けた。自分が運転しているという自覚はなかった。
気がついたら川べりの蛍の宿に来ていた。蛍の宿はもうどれも閉店だ。日が暮れても宿はなかった。
次に志乃が意識を自覚したとき、どこをどう走っているのか。暗い道の光の帯の中にいた。突然、大きな光のかたまりが太陽が落ちてくるようないきおいで近づき、志乃の頬のあたりをかすって流れた。その瞬間、志乃は大きな男の顔にあるものすごい目を見た。
志乃が反対車線を走っていることに気づいたのはその直後であった。
こんなに暗くなるまで、自分はどこにいたのだろうか。志乃は用心をしながら安全な場所まででることができた。
志乃は部屋に戻ってから、無性に寂しくなった。せつなさのまざった寂しさは、多くの人と別れなければならない死の瞬間に感じる感覚のようだった。すべてを失ったわけでもないのに全てから見放されたもののようだった。
ぼんやりしていた志乃の耳にけたたましい電話の音が入ってきた。電話の音が人によって変わるわけではないが、志乃には電話の音で蛍たちの顔が頭に浮かぶ。案の定、公彦の声だった。
「頼むよ。私が死にそうだ。頼む、すぐにきてくれ」
心を病んだ息子との二人暮らしは大変であろう。
「わかった。できるだけ早くに行く事にするわ」
志乃は東京を離れることに決めた後、三匹の蛍にはがきを出した。
「前略、このたび私の都合により、蛍の宿は閉店することになりました。みなさまには永らくご厚情を賜りましたこと、深く感謝します。これより先は皆様のご健康とお幸せをお祈りして参ります。くれぐれもお体を愛おしみくださいますよう。
かしこ
蛍の宿亭主」
三枚のハガキを志乃は翌日投函した。ハガキを投函したのち、志乃は信介が署名捺印をした離婚届を燃やした。裕一の遺言状も火に返した。
そのときになって志乃は男が残した小箱を思い出した。
ダイニングボードの上に置いてあった紫の袱紗に包まれた小箱を手に持って、膝の上で開いた。
古空壺焼きの夫婦茶碗の一つであった。茶碗の底に小さな紙切れがあり、
「一つは私が墓の中まで持って行きます」
と書いてあった。
志乃は体中の身の毛がよだつのを感じた。
どうにも訂正がきかないやり方だ。いったい男は存在したのだろうか。志乃が心の中で捏造したものではなかったか。
志乃は目の前に置かれた蛍焼きのひとつである、これこそ幻の古空壺焼きをじっと見つめていた。
数日後、哲郎が訪ねてきた。
「あんなおかしなハガキを寄越して、どうしたの」
「あたし、東京を出るのよ。鳥取で暮らすつもりなの」
「鳥取県のことかい?またずいぶん遠いところへ行くんだねえ。
でも、すぐ帰ってくるさ」
「戻らないわよ。あたしは雌蛍だもの。てっちゃん、雌蛍ってね、交尾をしたくなるとね、他の蛍の嗅いや光を真似してね、誘ってはいけない雄まで誘って交尾したあとは証拠を残さないように、食べてしまうのですって。怖いのよ」
「へえ、珍しいこと知っているのだねえ。それで、生まれる子はどっちの種類なの」
「知らないわよ。知る必要はないもの。とにかく、蛍って光を失ったら醜い姿になるけれど、光っていてもみっともないことするものなのね。外国では害虫なんですって。貴重な微生物や植物を食べちゃうらしいわ。てっちゃん、知っていた」
「そうなのかい。どっちでもいいけど、今度戻るときは俺のところへ戻れよ。一緒に酒に浸るのも悪くないぜ」
「ありがとう。てっちゃんは、私の正体なんてどうでもいいんだね」
志乃はそれぞれの蛍のそれぞれの反応を無視して、東京から七百キロも離れた蛍の宿へ飛び立っていった。