
■ 蛙 水
・ 新涼の今朝はネクタイ締めて行く
・ 菊活けて己が自慢の床柱
・ 耳鳴りは絶えずしており彼岸花
・ ビルビルに残業の灯ともりをり
・ 朝寝して読書に更ける初秋の夜
・ 素畳に初秋の冷えを覚えけり
・ 赤トンボ知らぬ都会の子らもあり
・ 背曲げて縁に瓜切る秋日和
・ 秋澄むや洪水(みず)去りし街々愁いなく
・ 納屋裏は荒れしままにて柿熟るる
・ 草に寝て初秋の空に絶叫す
・ よしず小屋今はさびれて秋の雲
・ 民宿もさびれ浜に人の影もなし
・ 里の庭今年もたわわ柿熟す
・ 純白のシーツ干しあり葉鶏頭
・ ・ 只今と玄関入ればちちろ止む
・ 座布団の欲しくなる頃夜の冷え
□ 父と母、それぞれの俳句ノート見つかりました。これで「蛙水」、「艶子」、そして「伝馬」と3人の春夏秋冬の句が出揃いました。
■ 艶 子
・ 久方の友三人と葛桜
・ 時の日や二階と下に鳴る時計
・ コスモスにコスモスの風昼の月
・ ころがりし空瓶の数秋深む
・ 在りし日の夫思いて萩の庭
■ 母が俳句を始めたのは、父が天に召されてからのことでした。俳句を読んだ歳月は、父よりずっと短かったですが、句のレベルは大変高いように思いました。父の句は素直すぎですが、母の句は正に俳句といえるものがあります。
■ 伝 馬
・ 大歩危峡下る二人の舟彩彩 大歩危・小歩危峡
・ 貫之の住処の跡や萩ゆれぬ 紀貫之、土佐日記
・ 国分寺お遍路憩う菊の庭 土佐国分寺
・ 朝焼けを横切て行きぬ雁の群れ
・ 孫迎え残暑厳しき庭に立つ
・ 孫と見る皆既月食雲切れ間
・ 鈴虫や籠あずかりて涼を待つ 鈴虫の飼い方
・ 禅寺や三門くぐり紅葉狩る
・ 教師会卓上飾る庭の菊
・ 手造りの味噌を味あう秋深し
・ 朝毎に柿味わいて友想う
・ 鈴虫の凛凛と鳴きて母ひとり
・ 五色台讃岐うどんに秋の空
■ 四国教区会が持たれ、今回は香川教会に赴きました。宿泊は「休暇村・讃岐五色台」で、部屋から見える瀬戸大橋の眺め、昼も夜も大変印象的でした。
・ 人去りてウミネコ濱に群れなしぬ
・ 皇族を迎え旗ふる秋日和
・ しまなみの秋の陽浴びて海渡る
・ 金木犀香る夕暮れ城を出づ
■ 今治教会に奉仕に赴いた折、今治城としまなみ街道―その一区間を走ってみて―を見学してきました。
・ 故郷や路地裏歩む妻の秋
・ 海鳴りやサーファーたちの秋到来
・ 紅葉の奥大山や岩魚食う
・ ぶなの森秋の陽透けて万華鏡
・ 栴檀の落ち葉に続く柿落ち葉
・ 洗礼の恵み新たに秋桜
・ 秋の雨聖き求めてみふみ読む
・ 宣教の祈りを燃やせ文化の日
・ 住みなれし街を後ろに秋の空
・ 学院もここかしこにて秋の風
・ 石仏やいにしえ語る秋の雲
・ 秋の日や松島一望蕎麦啜る
・ 松島や芭蕉を偲び歩む秋
・ 下北の海穏やかに旅の秋
■ 仙台での宮城聖化大会の奉仕を終えて、大湊教会・秋の特別集会に赴きました。
・ 宍道湖や秋の夕暮れ人集う
・ 金木犀薫る和の庭へるん邸
■ その次の週は松江での所用、一泊して、宍道湖の夕陽、ラフカディオ・ハーン(小泉八雲)の記念館、そして旧宅を訪れてきました。
・ 白菊や人無き庭にひとり咲
・ V字形描きて雁の渡し行く
・ すすき立つ墓前に偲ぶ在りし日々
・ 木犀の薫る小道や土佐の宿
・ 蜜蜂も菊のトンネル潜り抜け
・ 一番の朝の冷え込み知事退任
私が外国に行って不在中に、父が毛筆で清書し句集として作ってくれたもので、和綴じになっています。
画面右手にある手帳は、父の俳句手帳で、ボール・ペン書きでびっしり、折々の句が書き記されています。
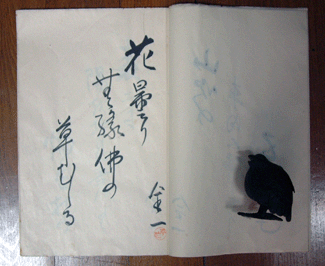
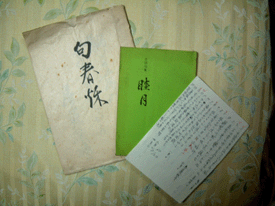

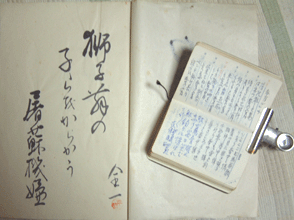
・ 親子3人の句集の名称は、父が書いた「句春秋」から取りました。(実際に使われている漢字は、「火」偏に「禾」の部首からなる漢字です。読みは「しゅう」、「集める」の意味で、そこから「秋」の時期をあらわす字として用いられたようです。残念ながら、ワープロで打ち出せません)。2枚目の写真をご覧ください。右手は、母の俳句メモと、合同句集「睦月」です。
・ フィリップの俳句の幾つかは、英語に訳しましたので、他のページに移しました。