
■ 蛙 水
・ 夏の夜をテレビドラマに興じけり
・ 真夜中に夏掛け布団たくしあげ
・ 廃船に小波寄せる初夏の海
・ 晩夏の夜妻雑事に余念なし
・ 窓明けて晩夏のネオン楽しめり
・ 過労ゆえの脚のむくみか晩夏の夜
・ 捨て扇筆一筋に書きなぐる
・ 豪雨禍の報に倅へ便り書く
□ 父と母、それぞれの俳句ノート見つかりました。これで「蛙水」、「艶子」、そして「伝馬」と3人の春夏秋冬の句が出揃いました。
■ 艶 子
・ すそわけの又すそわけの新茶かな
・ 万緑や動き続けの万歩計
・ 解禁の川黙々と遠嶺かな
・ 意志曲げぬ朝顔の白水をやる
・ 夏休みハッピが似合うバイト生
・ 夏休み家具置きかえて風の道
・ 引越しの仔犬さよなら朝曇り
・ リヤカーの氷り切る音日本橋
・ 追いかけて紙魚逃したり阿呆なり
・ 鉄線の白のこぼれて喪の帰り
・ ゴキブリに一瞬の殺意読経中
・ 満たされし一と日を記す竹風鈴
・ 駆け込みて帯びとくひまの暑さかな
■ 伝 馬
・ 新緑や眩しき土佐の3年過ぐ
・ 新緑や仁淀に泳ぐ紙の鯉
・ 学院の静けき日々や衣替え
・ キリスト者みことば学ぶ走り梅雨
・ 初物の枇杷日曜の朝餉かな
・ 初鰹食らいて土佐の人となる かつをのたたき
・ 七変化竜馬に学ぶ心意気 坂本竜馬
・ 紫陽花や心そぞろに名月院 あじさい街道
・ よもぎ餅新茶携え友来る
・ 呼ぶ声や山桃を手に友たてり
■ 春野町まで奥さんを連れ出されたとのことで「丁度農協で売っていたから」と、高知の特産品・山桃を届けてくださる。「洗わずに塩をまぶして、今日のうちにね」とことばを添えて。 ご馳走さまでした。
・ 梅雨の入り孫も詠むなり五七五
■ 小学生の孫から来たメールには「しちへんげ梅雨の訪れ告げている」とあり、また、幼稚園児の女孫からは「おじいちゃんいつもえがおだやさしいな」とありました。
・ 異国の客人多し初夏の奈良
・ 猿沢の池に遊びぬ五月晴れ
・ 五重塔緑の木々を従えて
・ 新緑やせんべいねだり鹿集う
・ 甘樫の丘に緑の風そよぐ
■ 5月半ば、奈良・王寺教会での御用がありました。御用が終わって、奈良の名所を訪れることができました。
・ サックスの音色響きぬ梅雨晴れ間
・ 梅雨の空恵みに保たれ共に集う
■ 6月には、熊本でのきよめ派連合聖会(4回の当務)とインマヌエル教会での礼拝の御用がありました。熊本は、既に入梅後でしたが、2日間、天候が保たれて、5つの教会から多くの方々が集われました。その様子は、会場となった熊本ナザレン教会の牧師・中出牧夫先生のブロッグ「jtjmakio.blogspot.com」でご覧ください。
・ 姫ボタル此処に彼処にせわしなく
・ 姫ボタル星と競いて草の上に
・ 闇に舞う小さきホタルや帝釈峡
・ 隠れ湯の川面かすめて燕飛ぶ
・ 信玄や燕飛び交う阿智の里
・ 朝市のきゅうり手にして阿智の川
・ 浦富のビーチバレーや海開く
■ 7月19日、浦富海岸でビーチバレー大会が開かれました。礼拝に向かう途中で見た浜は、多くの若者で賑わっていました。牧谷海岸でも海の家の準備が整い、いよいよ本格的な夏の到来です。
・ 白百合の凛々しく立てる暑さかな
・ 烏賊干しの網代港や夏陽射す
・ 烏賊釣りの舟の灯火沖に見て明日は晴れると思う夜なり
■ 明年(2010)の正月の歌会の題は「光」?でしたでしょうか。
・ 初蝉や鳴き声もなく地に生れぬ
・ 夕闇や花火に見入るキャンプの子
・ 賛美あり花火もありてキャンプの夜
・ 真夏日の暑さにめげずかずらかな
・ 聖会や肥後の朝顔露に濡れ 肥後の朝顔
・ 樹々静か風待ち月の暑き夕
・ 競い合う十七文字や夏の宴
・ 真夏日も四十九日で終わりける
■ 今年の高知の夏は、過去2年に比べて異常に暑く、7月4日に始まって、真夏日が49日間続きました。そして、1日途切れて、また翌日からは真夏日の再来です。
私が外国に行って不在中に、父が毛筆で清書し句集として作ってくれたものです。
画面右手にある手帳は、父の俳句手帳で、ボール・ペン書きでびっしり、折々の句が書き記されています。
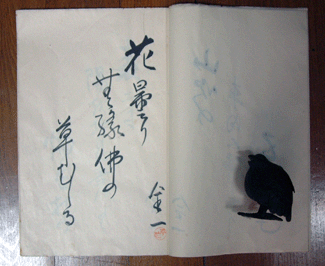
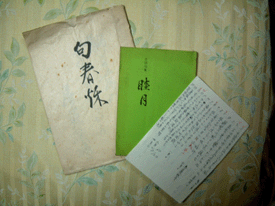

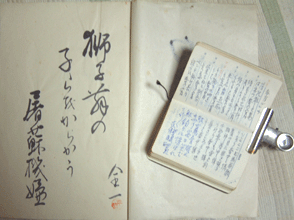
・ 親子3人の句集の名称は、父が書いた「句春秋」から取りました。(実際に使われている漢字は、「火」偏に「禾」の部首からなる漢字です。読みは「しゅう」、「集める」の意味で、そこから「秋」の時期をあらわす字として用いられたようです。残念ながら、ワープロで打ち出せません)。2枚目の写真をご覧ください。右手は、母の俳句メモと、合同句集「睦月」です。
・ フィリップの俳句の幾つかは、英語に訳しましたので、他のページに移しました。